インタビュー
墨田区新保健施設等開設準備室
平山氏 乾氏 一色氏 讃岐氏 猪俣氏
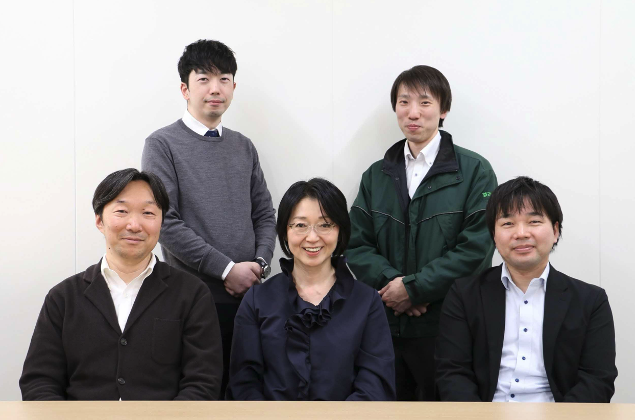
多様化・複雑化する課題に対し、部門横断で対応できる体制を構築
「すみだ保健子育て総合センター」開館の背景には、まず、向島と本所にあった保健センターの老朽化がありました。いずれも築50年ほどの建物で、本所保健センターにはエレベーターが設置されていないなどバリアフリーの観点でも課題がありました。加えて、保健、子育て、教育に関する課題の多様化・複雑化があり、部門を横断して対応できる体制を整えようという機運が高まっていました。こうして、2017年に「墨田区新保健センター等複合施設整備基本計画」を策定。計画に基づき、整備を進めてきました。
実際に場を利用する区民や職員の声を取り入れた空間づくり
空間づくりに際しては、実際にこの場所を使うことになる区民や職員の声を可能な限り取り入れようと、区民を対象にしたアンケート調査、職員を対象にしたワークショップやヒアリングなどを実施しました。
なかでも印象的だったのが、3回にわたって行った職員向けワークショップです。若手からベテランまで20名ほどの職員を集め、どのような働き方をしたいか、そのためにはどのような働く場になると良いかなどについて話し合い、意見を出し合いました。さらに、コクヨのライブオフィスを訪れ、オフィス空間や社員の方々が働く様子を視察したり、実際にイスに座って座り心地を試したことも印象に残っています。視察には保健所で働く予定の職員約9割が参加し、新しいワークプレイスやワークスタイルに触れる貴重な機会になりました。
苦労したのは、拾い上げた区民や職員の声をどこまで取り入れるかという判断や調整です。物価の高騰が進むなか、建設費用の再調整や内装・什器のコストダウンの検討をせざるを得ない状況になり、限られた予算の中でいかに実現するか、何度も打ち合わせを重ねました。
「くつろぎ」をコンセプトに、来館者がホッとひと息つける場に
区民が利用するスペースについては、「くつろぎ」をコンセプトにしています。当センターは、妊産婦の方、子どもの発育に不安を抱えている方、不登校のお子さんをもつ保護者の方など、デリケートな相談で来館されるケースも多い施設です。そういう方々がホッとひと息つける場にしたいという思いから、座りやすいイスを置いたり、木目調とグリーンを基調にした色合いにしたりしています。また、災害発生を想定し、常時・非常時にかかわらず分け隔てなく使うことのできるフェーズフリー*の什器を採用したり、壁にはポスター類を掲示せずデジタルサイネージで情報を発信するなど、変化に迅速に対応できる可変性のある空間づくりを目指しました。

区民ラウンジ
利用者を対象にしたアンケートでは、大半の方から「(3つの機能が)1つに集まってよかった」という声をいただいています。保健師、栄養士、保育士など専門スタッフが連携して業務にあたっていることへの安心感は大きいと感じています。
*フェーズフリー:日常と非常時を切り離さずに一体として捉え、災害や非常時に備える考え方。
自然とコミュニケーションが生まれ、快適に働ける空間に
職員の執務スペースにおいては、当センターのコンセプトである「つなぐ・つながる」を軸に、自然とコミュニケーションが生まれ、快適に働ける空間づくりを目指しました。什器はフレキシブルに使用できる点を重視して選定し、デスク用のイスには健康に配慮した機能的なものを採用しました。共用スペースには、個人作業が可能な集中ブースや即座に打ち合わせのできるファミレスブース、休憩や昼食の場所として利用できるコミュニティラウンジを設けています。

コミュニティラウンジ
また、新しい働き方として、グループアドレスを採用しています。課ごとに執務エリアを定め、エリア内のどの席で働いても良いというルールにしています。また、個人ロッカーと「モバイルバッグ<モ・バコ>」を一人一つずつ用意し、荷物はそこに納めてデスクの上に置きっぱなしにしないようにしました(クリアデスクの徹底。)。以前の執務スペースでは、各自のデスクに書類や荷物が山積みという状況が常態化していたので、劇的に変わりました。移転前は、自席がないことや文書などの荷物を減らすことに対して一部の職員からはネガティブな声が挙がっていましたが、実際に働き始めてからは「やってみたら意外とできた」「思いのほか快適だった」という声が多く、不満は届いていません。
「オフィス改善委員会」を中心に、より快適で働きやすい環境を目指す
新しいオフィスになり、職員からは「空間が明るくオープンになり、みんなの顔が見えるようになった」「周囲の課の様子も目に入り、いろんな人と話をするようになった」といったポジティブな声が多く寄せられています。特によく使われているのがファミレスブースです。会議室よりも気軽に使えて、「パッと打ち合わせをしたいときに便利」という声が届いています。また、コミュニティラウンジなどに置いている、座面が360度揺れるバランスボールのようなイス「ingLIFE<イングライフ>」も好評で、視察に来た方々もみなさん興味をもたれます。
一方、集中ブースについては思いのほか利用者が多くなく、認知度が足りないのか、周囲の目が気になって使いにくいのかなど検証が必要ですが、利用促進をしていきたいと考えています。また、コミュニティラウンジは昼食時には多くの職員が利用しているものの、仕事をする姿はあまり見られません。他部門の職員同士のコミュニケーションが活発化するよう、引き続き施設内ABW*を推奨し、職員の意識や行動が変わっていくことを期待しています。
また、以前から推進していたペーパーレス化に加えて、文房具類を共用化したことで物品の削減なども進んでおり、仕事が終わったら片付ける「クリアデスク」のルールも浸透しています。さらに、快適で働きやすいオフィスの持続に向け、「オフィス改善委員会」を立ち上げ、自分たちのオフィスをどう使いたいかを話し合っています。
引き続き区民や職員の声を拾い上げ、当センターがより良い場になるよう努めていきます。
*ABW:アクティビティ・ベースド・ワーキングの略称。業務における活動に合わせて、自ら働く場所や時間を選択できる働き方を指す。
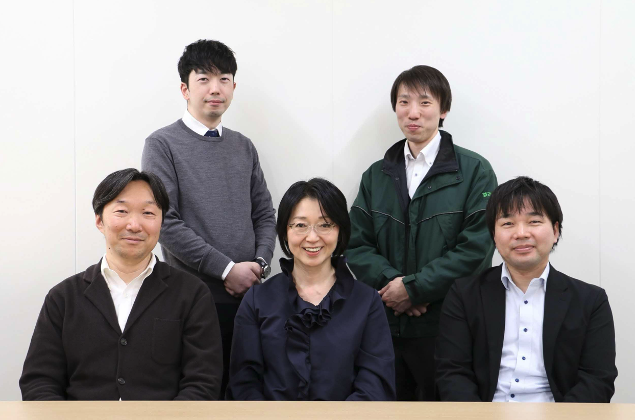
墨田区新保健施設等開設準備室のみなさん。
下段左から、乾氏、平山氏、一色氏、上段左から、讃岐氏、猪俣氏。






























コクヨ担当者
空間づくりにおいて、施設で働く職員の声を反映させたいとのご相談をいただき、職員を対象にしたワークショップの開催や、弊社品川オフィス「THE CAMPUS」への視察の企画をさせていただきました。新しい働き方を実践している社員の姿を見ていただいたことで、ABWや固定席を持たないグループアドレスなどの新しい働き方へのイメージをポジティブに捉えていただくきっかけになったと思っています。
また、多様な人が集まる場所として、日常と非常時を切り離さずに一体として捉え、災害や非常時に備えるフェーズフリーの考え方などをご提案し、実際に取り入れていただきました。
区民や職員のみなさまからも満足の声をいただいているとお聞きし、大変嬉しいです。今後もより多くの方に快適にご利用いただき、施設が最大限活用されることを願っています。
コクヨマーケティング
野本 直哉、森永 陽子
コクヨ
清水 康伸、住田 薫