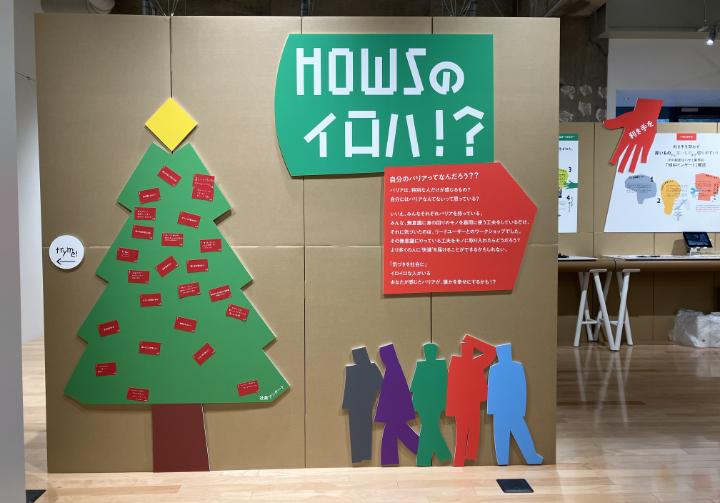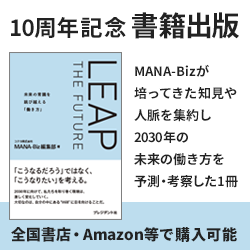仕事のプロ
組織の成果を決める"見えない力"とは?〈前編)
組織心理学で明らかにする、人間関係の「投資」効果

コロナ禍によって変化した働き方は、チーム内の人との距離感やコミュニケーションのあり方も変えた。業績を伸ばすために必要な打ち手は生産性や効率化が最良だと思われがちだが、実は組織心理学の観点で見ると、「人間関係が最も費用対効果の大きい投資」だと言う。チームの成果を最大化する関係性づくりについて、立命館大学スポーツ健康科学部の山浦一保教授に伺った。
チームパフォーマンスに もっとも影響するのが「人間関係」
――早速ですが、組織心理学とはどういう学問なのでしょうか?
組織心理学とは、組織のトラブルの原因を特定し、うまくいっている集団に共通するリーダーシップや人間関係を明らかにして、組織のパフォーマンスを高めることを目的とした学問です。組織の一人ひとりがより幸せになるのと同時に、対人からチーム、組織と関わる単位が大きくなることで、一人ではできないことを実現できる。しかもより早く、よりよいカタチで提供できるようになる。そのためにどうすればいいか考えるのが組織心理学です。 人間である限り、幸せは人と人との関わりのなかでこそ得られるものです。実際、ハーバード大学の有名な「グラント研究」の結果から、人間の幸福と健康を高めるのは周囲とのあたたかな人間関係やつながりであることが証明されています。また、スポーツチームのトップ選手とチームのパフォーマンスの結果に関する研究からも、メンバー同士の関係性が、個々の能力と同じくらい重要であることもわかっています。
組織を支配する5つのネガティブ要因
――それだけ人間関係が重要だということですが、関係性がうまくいっていない組織では、原因としてどのような傾向が見られるのでしょうか。
組織を支配するネガティブな要素には、「妬み」「温度差」「不満」「権力」「信用(不信感)」の5つのテーマがあります。 実はこの5つのうち、「不満」が私の研究の出発点です。組織のメンバーが飲みにケーションで、相談といいつつ愚痴を吐き出すのは重要なことだと気づいたからです。 不満を抱くのは、組織に期待や関心があるから。期待と現実との間に「もっとこうだったらいいのに」などのズレがあるから不満が生まれ、そもそも期待がなければ、不満の前にあきらめてしまうはずです。
――期待や関心があるから「不満」が生まれて、そこからほかの4つに広がっていくわけですね。
はい、不満はどういう原因から発生するのか、どんな時に起きる現象なのかを掘り下げていくうちに、他の4つのテーマに派生していきました。
その一つの例が「温度差」です。自分のモチベーションは高いのになぜあの人は低いのかなど、温度差に対する不満が人間関係やリーダーシップの問題へとつながっていくのです。
ただ、モチベーションの温度差を埋めることが重要なわけではありません。例えばチーム全員が異常なほどモチベーションの高いなかで働き続けるとしたら、あまり居心地がいい環境とはいえませんよね。モチベーションの波はあって当たり前。高い人もいれば低い人もいるし、同じ人の中にも高い時と低い時があります。その温度差を無理やり高い状態に矯正する必要はなく、差があっていいのです。「今は下がっている時だな」などお互いの状態に気づき、思いやりを持って配慮し合う。あるいは、モチベーションの高い人と仕事をすることで、「この人みたいにイキイキと仕事ができるようになりたい」と憧れを抱ける関係性をつくることが大切なのです。
また、自分のモチベーションの凸凹を感じ取り、自己調整することができれば、おのずと対人関係にも活かすことができるはずです。まだ議論の最中ではありますが、最近の研究のなかで「ネガティブもポジティブも含めて個人の中の感情が、多様で揺れ動いている人のほうが健康だ」という説もあります。自分の中の凸凹をできるだけ抑えて均一にしようとすると無理が生じますし、相手にも均一であるよう求めてしまいます。せっかく多様性の時代なのですから、もっと凸凹を楽しむくらいでいいと思っています。

よりよい関係性を築くために、 経済的資源と情緒的資源を「交換」し合う
――同質化させようとするのではなく、メンタルの状態も多様でいいということですね。
「相手と自分は違う」という前提に立って、お互いに「資源の交換」をしていくことが大切です。ここでいう資源とは、情報や人脈、教育プログラムへの参加の機会といった経済的資源だけでなく、笑顔やあいさつ、目線を交わす、しっかり話を聞くなどの情緒的資源も含まれます。 上司と部下は出会った瞬間からさまざまな形で資源の交換を始めます。特に出会ってすぐの10分程度のわずかな時間に、あいさつや雑談をする、目を見て会話するなどの資源の交換があったかどうかが関係構築に大きく影響することが、実験結果から明らかになっています。つまり、関係性を築くには「初期投資」が重要だということです。なかでも目線を交わすなどの「視覚」と、声のトーンが与えた印象は関係性構築において大きな影響があるようです。 ある会社で、他の工場ではメンタル不調を訴える社員が複数人出ているのに対して、工場長が毎朝社員に声をかけていた工場だけは一人もいなかったという事例もあります。こまめなコミュニケーションを取ることは面倒だと思われがちですが、それは「コスト」ではなく「投資」なのです。こうした資源の交換が行われなくなると、組織の中で「身内」と「よそ者」といった「内」と「外」の分断が始まってしまいます。
――最初の10分が重要だと知らずにいい加減な対応をしてしまったとしたら、もう部下との関係性はうまく構築できないのでしょうか?
第一印象づくりで失敗したとしても、リカバリーすることはできます。例えば、たまたま同じ自動販売機の前に立った時や、食堂でレジを待っている時などは絶好のチャンス。こういう機会にさりげなく声をかけるなど、ほんのちょっとやりとりをするだけでも、関係性を築くことにつながるはずです。 私自身、新人時代に飲料の補充に来られていたメーカーの方に「元気?」と声をかけてもらえたことが嬉しくて、毎日同じ時間に自動販売機に行くようにしていたことがありました(笑)。 組織にはさまざまな形で人が関わっていて、そうした人達と資源交換する大切さを教えてもらえた出来事でした。
互いの凸凹に配慮し合い、 成長しあえる心理的安全性を担保する
――組織のコミュニケーションのあり方は、どういう状態が理想的なのでしょうか。
人がある程度集まると、どうしても「内集団」(身内)と「外集団」(よそ者)に分断されがちですが、チーム全員が「身内」だと感じることが大切です。人数が多すぎると全員を見きれないと思われるかもしれませが、上司一人で全員を見る必要はなく、役割分担すればいいのです。ただ、人に任せすぎて上司がまったく現場を見なくなると、部下に目線を送っていないことになり、言いたいことが伝わりにくくなる。部下が「この人が言うことなら」と感じられないなら、その組織の形態は意味をなしていないことになります。コミュニケーションの流れがうまく機能するように組織は形作られているはずですから。リーダーはできる限り日常的に現場に出て必要なコミュニケーションを取り、外集団をつくらないようにする必要があると考えます。 また、チーム内に存在するさまざまな凹凸は、ならして平らにしようとするのではなく、組み合わせることも大切です。自己開示をし、お互いの凸凹を理解したうえで、相手のいいところは褒める、不得意なところにはヘルプを出せる。つまり自分の持っている資源を与えて、別の機会には相手の資源を受け取ることで、チーム全体の土台が強くなっていくわけです。 例えば共同作業で相手が困っている時に助けることで自身の成長を感じられることも資源の交換ですし、関係性がうまくいっていない組み合わせがある場合は、お互いの言い分を聞く場を持つことも同様です。そういう関わりのなかでお互いに成長し、結果的に底上げになっていく。そんなやり取りができる雰囲気や環境、人間関係があるチームが、心理的安全性のある組織なのだと思います。 後編では組織心理学から見るアフターコロナのあるべき組織やオフィスのあり方について伺います。

山浦一保(Kazuho Yamaura)
2010年より立命館大学スポーツ健康科学部准教授、2016年より現職。専門は産業・組織心理学、社会心理学。長年にわたって企業やスポーツチームにおける「リーダーシップ」と「人間関係構築」に関する心理学研究に従事。著書に『武器としての組織心理学』(ダイヤモンド社)、『チームが変わり生産性が劇的に上がる!心理的安全性の築き方見るだけノート』(宝島社)ほか。