インタビュー
京都工芸繊維大学 仲隆介教授
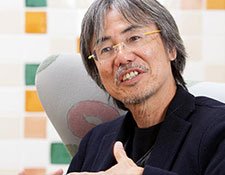
——— 今回西予市のオフィス改革に参画されましたが、最初に意識したことは。
仲教授
オフィスっぽいデザインにしたくなかったので建築家を呼ぼうと、空間設計はOpen
Aの馬場正尊さんにお願いしました。最初の発想・企画は馬場さんと我々の研究室とで進めました。今回のオフィスはABW(Activity Based
Working)の考えに基づいたデザインで、モデルとなる部署に所属する職員は、固定席メンバーを除いて、4階フロア内で働く場所を自由に選べるようになっています。またオフィスだけでなく働き方も改革をする上で、産業心理学の戸梶亜紀彦氏教授(東洋大学教授)にもメンバーに入ってもらいました。参画は市の指揮役になっていた総務省出向の企画財務部長
大平利幸氏(現・内閣官房IT総合戦略室参事官補佐、 西予市政策アドバイザー)からの要請でしたが、職員に受け入れてもらいやすい表現やコミュニケーションをデザインする上でとても有効でした。

——— 働く「場」と「働き方」と、職員にとってはソフトとハード双方からの改革ですね。
仲教授
オフィス改修の前後で職員アンケートや行動観察調査を行い、効果測定をしてみると、面白い結果が出ました。1日かけて行った行動観察では、課を越えたコミュニケーションが増えたことが明らかになりました。また、定性的なアンケートにおいては、『コミュニケーションから価値ある情報を得る機会が増えたか』という問いに7割の人が増えたと回答。『好きな場所で働く、動き回ることで効率が上がったか』という問いに、「上がった」と答える人が多い。また、会議に関しても、会議室が確保できなくて会議を延期する回数が減り、かつ移動距離も削減できたという結果に。その他には思い切って書類削減を行いペーパーレス化を進めたことで、書類検索にかかる時間が削減できたという結果も出ています。そして意外なことに、「働き方の変化によりストレスを感じたかどうか」という問いの回答から、新しいオフィスで働くことへのストレスはあまり感じていないことが分かりました。

——— オフィス改革後に職員の不満が少ないというのは、否定的な意見もあった当初からは想像できない結果ですね。実際に新しい働き方や新しいオフィスを使ってみると、職員自身がメリットを実感できたと。
仲教授
そうだったのだと思います。これは今回オフィス改革を進めるにあたり、モデル事業対象部門で4階に在籍する職員のみなさんを対象として約1年かけてワークショップを行った効果でもあります。先ほどのアンケートの中で、戸梶教授は労働価値観(働く目的・働く上で重要と思うこと)と仕事のやりがいとの相関関係について調査されていますが、その結果が興味深いです。
オフィス改革以前は「達成感」「同僚への貢献」「社会的評価」「所属組織への貢献」が得られる仕事にやりがいを感じる結果でした。ところが、改革後の調査では、「達成感」「同僚への貢献」「所属組織への貢献」に対して変化は無かったものの、改革以前に高かった「社会的評価」の相関関係は下がり、代わりに「社会への貢献」の相関関係が上がりました。且つ、オフィス改革以前には相関関係が見られなかった「自己の成長」という項目において、改革後では相関関係が見られるようになった。つまり、"仕事を通じて社会から評価されたい"、"認められたい"という状態から、"仕事を通して社会に貢献したい"
"成長したい"と感じるように変化したわけです。これは、ワークショップなどを通じて職員と議論を重ねた上でオフィスが変わり、新しい働き方を経験したことにより生まれた変化です。職員の意識がより自律的に、能動的に仕事に向き合うように変化したことの表れではないでしょうか。
——— 職員の意識がそこまで変わるのですか。西予市が成功した要因は何とお考えですか。
仲教授
いくつかありますが、ひとつは始まり方ではないでしょうか。オフィス改革に係る産学官連携協定を結び、記者会見を行ったことにより、オフィス改革プロジェクトを進めざるを得ない状況を作り出せたことが大きいと思います。また別の理由として、ワークショップでの意識改革の手法が挙げられます。意識改革というのは一般的に危機感を煽る、いわゆるホラーストーリーを語ることによる動機付けが行われますが、西予市の場合は東洋大学の戸梶教授の協力により、産業心理学を取り入れた意識改革が行われました。『職員数を減らさなければならないがサービスの質は落とせない、だから少ない人数でも同じパフォーマンスとなるよう業務効率を上げなくてはならない』と職員は頭では理解しています。ですが、「生産性を上げる・業務効率を上げる」=「今以上に負担が増える」と考えてしまっては働き方改革をすることに価値を見出せません。効率化することが自分たちにとって価値あるものだと理解できるようにならなくてはなりません。
その1つの例を挙げましょう。職員と議論した結果、4階では窓口対応のスタイルが変わりました。以前の窓口対応は、特に担当を決めず、窓口に訪問者があれば一番早く対応できる職員が誰と無く対応していました。そのやり方では業務中常に利用者に気を配らなければならないため、職員は自身の業務に集中しきれずパフォーマンスが悪かった。ワークショップでの問題提起をきっかけに、オフィス改革後は日替わりで窓口対応の担当を設けるスタイルに変更されました。カウンター近くに窓口担当席のテーブルを設けて、担当者は1日中カウンター前で業務を行いますが、そうたくさん来訪者がくるわけではないので自分の業務もそこで集中して行える。それ以外の職員は、終日自身の業務に集中できるというメリットを得ました。業務効率を上げるために従来のやり方を見直すことは負担ではなく、職員のメリットにつながることだと実感してもらいました。
——— 全員体制から担当制へ。市民の反応はいかがでしたか。
仲教授
来庁者アンケートの結果では、利用者の満足も高いことがわかりました。窓口へ行けばすぐに、その日の担当職員が対応してくれますからね。
——— 負担が増えるどころか職員も利用者もハッピーになった成功体験があると、他のことも変えてみたいと思えますね。
仲教授
働き方改革を組織で実現するためには、職員一人ひとりの生産性を上げなければなりませんが、ただ「生産性を上げる」だけでは、職員は果たして価値を見出せません。戸梶教授は、生産性向上が職員にどんな価値をもたらすかを、職員の目線に立って発信されていました。伝え方ひとつで、モチベーションに与える影響は驚くほど変わるのです。
































