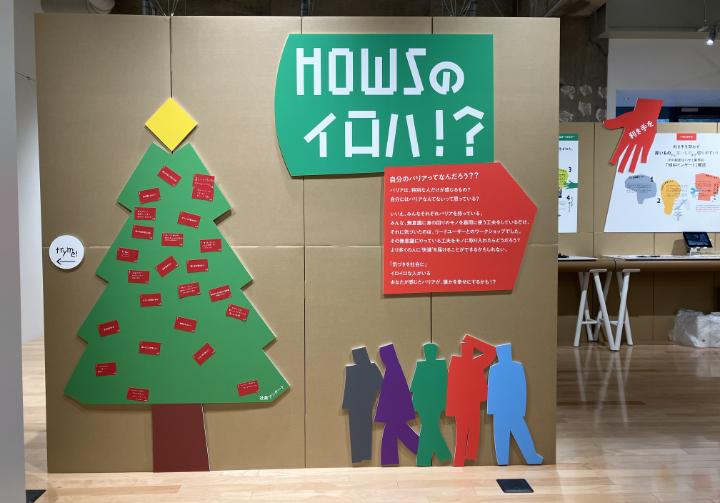仕事のプロ
2018.01.15
インクルーシブデザインの視点から見たダイバーシティ〈前編〉
一人ひとりの多様な個性を伸ばすために

多様な特性を持つ人がデザインプロセスに加わることで、社会の革新(イノベーション)を目指すデザイン手法、それがインクルーシブデザインだ。インクルーシブデザインを企業における商品開発や小中高生のキャリア教育にも採り入れている京都大学総合博物館の塩瀬隆之准教授に、インクルーシブデザインの視点から捉えたダイバーシティの現状と可能性について話を聞いた。
今の日本では、
ダイバーシティの本質が理解されていない
開発者だけでなく多様なユーザを巻き込んだデザインプロセスの有用性に着目したインクルーシブデザインを専門にする塩瀬氏のもとに近年ダイバーシティをテーマにした講演や研修の依頼が増えているという。その背景には何があるのか。
「企業がダイバーシティ推進に力を入れる大きな理由の一つは人手不足です。人数が絶対的に不足しているという意味ではなく、活躍してもらいたい力をもった人が減っているということです。以前であれば若手に任せていた仕事がいつまでも自分の手元にある、いつまでも顔ぶれの変わらないメンバーでやっている、という実感があるのではないでしょうか。同じ背景を持ったメンバーで組織が固まっているために、新しい切り口の発想も出てこない。そこで別の観点を持ち込んでくれる人が必要だということで今ダイバーシティが求められるようになっているのだと思います」
「もう一つは、2016年4月1日に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されたことです。行政機関や事業者には、障がい者へのReasonable Accommodation(合理的配慮と訳されている)を可能な限り提供することが求められるようになったことで対応を迫られているのでしょう」と語る。
だが、ダイバーシティの視点で、多くの企業が人材の確保やその活用を目的に取り組みを始めているものの、その本質がしっかりと理解されているとは言い難い状況だ、と塩瀬氏は指摘する。
「企業の中には、女性、障がい者、外国人の採用を増やせばダイバーシティになるだろうと思い込んでいるケースがあり、ダイバーシティを表層でしか捉えられていないのが残念です。たとえ経営層が、やれダイバーシティだ、オープンイノベーションだと叫んで部署までつくってしまっても、担当になった社員は何から手をつけてよいか戸惑っている状況ではないでしょうか」
「ある行政が開催した市民参加型の会議などでも、障がい者に出席してもらうものの、議論に参加してもらうわけではありませんでした。結局、会議の最後に少し意見を聞くくらいのオブザーバーとしての役割しか与えられていなかったわけです。そういう意味では、今までいなかった新しいメンバーがいることをただ容認しているレベルで、まだまだ特別扱いというのが現状でしょう」
「ある行政が開催した市民参加型の会議などでも、障がい者に出席してもらうものの、議論に参加してもらうわけではありませんでした。結局、会議の最後に少し意見を聞くくらいのオブザーバーとしての役割しか与えられていなかったわけです。そういう意味では、今までいなかった新しいメンバーがいることをただ容認しているレベルで、まだまだ特別扱いというのが現状でしょう」
日本になぜ
ダイバーシティが浸透しないのか
もともとダイバーシティは多民族がひしめく欧米から発した概念だけに、ムラ社会の意識が根強く残る社会で生きる日本人と欧米人とでは意識の根元のところで決定的な差があるのかもしれない、と塩瀬氏は指摘する。
「一番大きな違いは、"お互いがわかりあえる"と思っているか、"わかりあえない"と思っているかだと思います。日本人は、わかりあえない場合、お腹の中に違和感を抱えながらも最終的にわかりあえたことにする。欧米人の場合は、わかりあえないことを前提にしながら妥協点を見つけて前に進もうとする。だから日本の企業に欧米流のダイバーシティの考え方が持ち込まれると混乱が生じるのです」
そのために生じているミスマッチが企業における外国人留学生の採用でも見られるという。
「日本の企業には終身雇用の文化がまだ残っており、入ってきた社員を長い時間をかけて育てよう、という考えが根強いのに対し、留学生の中には自分の経歴に日本企業で働いたことを1行書き足すくらいのつもりで入社してくる学生もいて、そこにギャップが生じています。日本の企業では、社員みんなを同じ正方形の型にはめようとし、突出した部分を削ってしまうタイルマネジメントを善としてきたために、違和感のあるものをそのままそばに置いておくことができず、それが社員一人ひとりの多様な個性を奪ってしまっているのではないでしょうか」と問題を投げかける。
ダイバーシティの必要性が叫ばれながらも、現場では多様性を排除している現実が浮かび上がる。
いずれ企業にもやってくる
大学の課題
置き去りにされたままの意識とは裏腹に、現場ではダイバーシティに対応せざるを得ない状況にいやおうなく直面している。先に塩瀬氏が言及した障害者差別解消法への対応もしかり。そして、塩瀬氏は大学で先鋭的に現れている事象はいずれそうした大学生たちが社会に出た時に企業が直面することになるという視点からいくつかの事例を提示する。
「大学の中には学生の多くを留学生が占める大学もあります。そして、留学生比率が高くなるにつれて顕在化してくる課題の一つにLGBTQ(レズ、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーをはじめとする性的マイノリティ)への対応があります。留学生にLGBTQが多いということではありませんが、一般的に海外の学生は日本の学生よりも自己主張をしっかりとすることが多く、自身の性についてもカミングアウトする傾向があるため、たとえば、ジェンダーフリーのトイレをどうするかという日本ではまだまだ対応が遅れている課題に向き合う必要性が大学に生じています」
「また、本人確認の点でも課題が浮き彫りになりつつあります。たとえば、在学中に性転換した学生の学生証変更に証明書が必要かどうかとか、社会人になってから性転換した卒業生は戸籍の名前も顔も変わっていて、なにをもって本人確認をして学籍証明を出せばよいのかと、判断を迫られるケースも出てきているそうです」と、企業へ今後の心構えを呼びかける。近い将来には、学習履歴の証明にブロックチェーンなどの履歴保証技術を駆使する必要がでてくるかもしれません。
前編では、ダイバーシティの推進が求められながら、日本人、また日本の会社組織が持つ特性ゆえ対応が遅れている現状を明らかにした。後編では、インクルーシブデザインの視点をダイバーシティに応用していくためのアプローチについて触れる。

塩瀬 隆之(Shiose Takayuki)
京都大学総合博物館准教授。京都大学工学部精密工学科卒業、同大学院修了。京都大学総合博物館准教授を経て2012年 7月より経済産業省産業技術環境局課長補佐(技術戦略担当)。14年7月京都大学総合博物館准教授に復職。共著書に「インクルーシブデザイン」など。日本科学未来館「“おや?“っこひろば」の総合監修者、NHK Eテレ「カガクノミカタ」の番組制作委員なども務める。