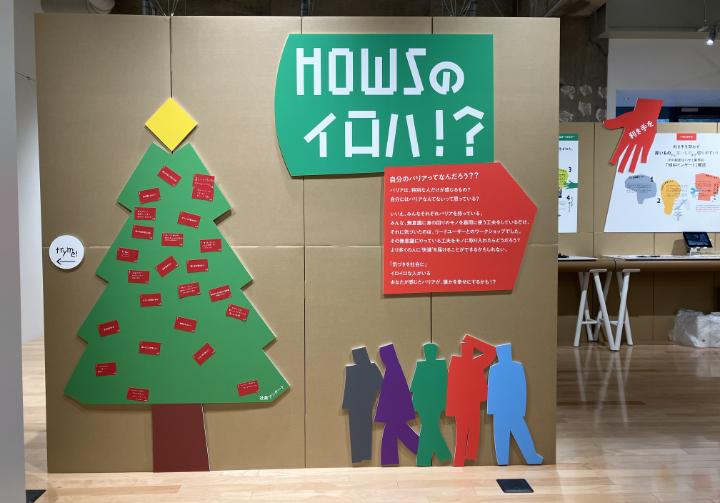リサーチ
2019.10.09
ハンディキャップを仕事に活かす!障がい者雇用のリアル
当事者・企業が抱える問題意識と解決への取り組み

2018年、民間企業への精神障がい者(発達障がい者を含む)の雇用が法律で義務化され、企業の採用活動が進んでいる。そんな中、障がい者に対する就職支援や職場定着支援を日本全国で行っているウェルビー株式会社は、ウェルビーのサポートを受けて就労したOBの就職先企業を対象に、2017年に『精神障害者・発達障害者について就労移行支援事業所が行う企業支援の試みに関する調査』を実施・発表しました。
精神障害者保険福祉手帳を持つ人が、2006年から“企業の障害者法定雇用率”の対象となり、2018年には雇用義務が厚生労働省から明示された。“障害者法定雇用率”とは、「障害者雇用促進法」によって義務づけられている、「常時雇用するべき障がい者の割合」のこと。精神障害者保険福祉手帳を所有しているのは、知的障害がない、あるいはごく軽度な発達障がい者や、うつ病やてんかん等の精神障がいのある人たちだ。
発達障がい者は年々増加していると言われているが、厚生労働省の調査研究では障がい発見率の向上が理由の一つであると発表されている。また近年、発達障がいに対する認識が深まったことで、幼少期や学童期に発見されるケースや、大人になってから『自分の不自由は障がいに起因する』と気づくケースも増加している。(※)
大企業では障がい者雇用のために特例子会社をつくっている所が多いが、発達障がいと診断される事例の増加に伴い、特例子会社の採用枠にはとても収まりきらないという現実がある。また、本体企業での就労を望む当事者も少なくない。義務化を受けて、特例子会社を持たない企業でも精神・発達障害者の採用が進んでいる※。
企業は精神・発達障がい者の雇用をどう考えているのだろうか。ウェルビー株式会社が行った『精神障害者・発達障害者について就労移行支援事業所が行う企業支援の試みに関する調査(2017年)』では、「精神・発達障がいのある方を採用する、または共に働く場面で課題を感じたことはあるか?」という質問に対して、94.9%の企業が「ある」と回答している。「安定した勤怠が保てるか不安(50.7%)」、「適切な指導がわからない(42.7%)」、「コミュニケーション面で不安がある(40.0%)」、「採用時に適性や能力を十分把握できない(38.7%)」等が上位にあがっている。
発達障がい者に関しては、ずば抜けた集中力があったり、特定の分野で卓越した能力を発揮したりするケースもあり、ハンディキャップが仕事に活きることがある。しかしその一方で、思いもよらぬところで特性由来の難しさを抱える当事者も多い。「2つ以上のことを同時にこなす」、「イレギュラーに対応する」等は最たる例だ。事務処理能力は抜群に高いが「お茶くみ」がどうしても苦手という当事者もいる。このギャップに企業は戸惑い、当事者も悩むことになる。障がい特性を理解し、活かしながら、共に仕事をしていくための取り組みが必要となる。
同調査によると、障がい者雇用に対して何らかの取り組みを行っている企業は96.2%。「職場実習を行っている(49.4%)」は、当事者が仕事を覚えるためだけではなく、企業が適性を把握するうえでも有益だ。「産業医・保健師・カウンセラーを配置している(44.3%)」は、症状の悪化や医療的介入が必要となった場合に、早期発見・対応できる点では好ましいが、より高い専門性を持つ人のサポートを受けられると、トラブルを未然に防ぐことも可能になる。本人の主治医との連携ができるとさらに良いだろう。「障がい者の職場指導・援助を行う担当者を選任している(30.4%)」や「企業内ジョブコーチによる支援を実践している(11.4%)」、「仕事以外の(生活等)相談を行う担当者を選任している(10.1%)」は、担当者に専門知識が求められるが、適任者が見つかれば、当事者にも企業にも心強い存在となる。
「得意」と「苦手」は障がい者に限らず誰もが持っているもので、健常者であっても個人の得手不得手に理解を得られず離職に至るケースが少なくない。発達障がい者の場合その差が非常に大きく、「苦手な部分」が健常者から見ると特異であるがゆえに、より理解が得られないことが多いといえる。たとえば「何度も説明しているのに覚えない」という現象は、ワーキングメモリー(作業記憶・作動記憶)が弱い当事者にとっては怠慢ではなく障害特性であるから、メモで指示をもらう、当事者が必ずメモを取るなどの対策が必要となる。
当事者は「企業が障がいを理解してくれない」と感じ、企業は理解したくても「どんな配慮が必要なのかわからない」と感じている現状がある。しかし、そのギャップはある意味必然だ。専門家や家族、あるいは本人さえも、個々の特性を十分に把握しきることは難しく、手探りの状態でベターを探しながら過ごしている。共通の傾向はあるがオーダーメイドの支援が必要で、やり方はともに構築していくしかない。疲れやすい、視覚や聴覚の刺激(例として、照明や話し声等)で気分が悪くなるなど、身体にあらわれる不調への理解も必要だが、ここは働き方改革でも推奨されている「柔軟な働き方」の導入が助けになる可能性がある。
精神・発達障がい者雇用には、当事者と企業間のコミュニケーションが不可欠であるが、擦り合わせに困難を感じたときは、就労支援を行う組織の活用や、主治医やカウンセラーとの連携を進めることで、改善が期待できるだろう。最終的には性格や価値観の違う個人同士が歩み寄るのと同じ温度感で、当事者と企業・同僚が距離を縮めていけることが望ましい。本人も周囲も特性を理解し適切な対応をしたとき、障がい特性は仕事上で大きな強みとなり得るのではないだろうか。
※公益社団法人日本発達障害連盟 研究報告書
【出典】障害者就労支援のウェルビー 「精神障害者・発達障害者について就労移行支援事業所が行う企業支援の試みに関する調査」