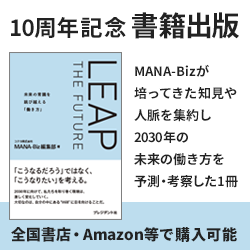仕事のプロ
「木を伐らない林業」を実践する中川の挑戦〈前編〉
未来のビジョンから逆算して「やらない業務」を決める

「林業」というとスギやヒノキの伐採をイメージする人が多いのではないだろうか。しかし、和歌山県田辺市を拠点に活動する林業ベンチャー、株式会社中川では、「30年後の和歌山に緑を」をビジョンとして掲げ、苗木づくりから植林、山林管理など育林に特化した林業を実践している。「伐る」部分を捨てて独自の林業ビジネスを展開する理由やメリットについて、創業者の中川雅也氏さんにお話を伺った。
子どもとの会話をきっかけに 林業ベンチャーを起業することに
――そもそも林業ビジネスに参入した理由は? 林業と出合ったのは、新卒で入社した商社を病気で退職したことがきっかけです。地元でたまたま求人があったのが森林組合だったので、林学を学んだこともないまま林業の世界に飛び込むことになりました。家庭をもってからも、早朝に出勤して深夜に帰宅する生活を疑問もなく続け、残業が当たり前でした。しかし、3歳の子どもとの会話をきっかけに「今の働き方をシフトチェンジする必要があるな」と気づきました。 ――お子さんと、どんな会話をなさったのですか? 子どもと遊ぶ時間がとれなかったとき、「お父さんはどうして仕事するの?」と聞かれ、「家族のためだよ。稼がなきゃみんな生活できないよ」と答えました。すると子どもは、「じゃあ僕、おばあちゃんにお金借りるよ。お父さんの1日はいくらで買えるの?」と質問してきたのです。僕は母子家庭で育ったこともあり、父親は仕事に全力で取り組むもの、という価値観をもっていました。でも子どもが求めているのは「違うお父さん像」だったと気づき、仕事のやり方をシフトチェンジする必要があるな、と実感したのです。 ここからの思い切りは早く、子どもと話した翌日に辞表を提出しました。仕事の引き継ぎなどもあり、実際に退職したのは約1年後になりましたが、まだ在職中だった2016年夏に、林業ベンチャーの株式会社中川を起業しました。 ――初めから起業を考えたのですか? 子どもと遊ぶ時間がつくれるよう、時間の自由度が高い就職先をまずは探しました。しかし、なかなか見つからず、「だったら自分が働きたいと思える会社をつくってしまおう」と考えて起業したんです。 ――なぜ林業ビジネスに取り組むことに決めたのですか? 林業で起業した理由は、前職で携わっていたためある程度のビジネスノウハウを知っていたことも一因ですが、林業のタイムスパンが自分の求める暮らしに合っていると感じたのが大きいですね。木は50年ほどの長い時間をかけて成木になるもので、育林は1分1秒を争う業務ではありません。ですから日々の山林管理なども、「50年のスパンで考えたら1日休んでも大したことはないな」と余裕をもって取り組めると考えました。家族との時間をつくりたくて起ち上げる会社なので、子どもたちの未来に役立つ取り組みをしたいと考え、「30年後の和歌山に緑を」をビジョンとして掲げています。
植林体験や広告宣伝業としての林業で 収益を生む
――林業ベンチャーとして、どんなあり方を目指して起業したのですか?
起業にあたっては、林業というビジネスをいったん因数分解し、自分たちでできる、またはやるべき部分だけを取り出して担うことにしたのです。林業の手がける領域は「木を植えるところから伐って売却するまで」が一般的ですが、すべてを手がけようとすると多様なスキルが必要となり、人材育成が大変です。そこで私たちは、「木を伐る」という工程はあえて担わず、育林を中心とした林業ビジネスを構築しようと考えました。
――なぜ「木を伐る」という要素を捨てることにしたのですか?
林業のサイクルの中でも、伐採はもっともスキルを必要とする部分であり、かつ危険を伴う作業でもあります。逆に言えば、「伐る」を手がけないことで、植林のプロを育成しやすいとも考えました。
また、森林組合で働く中で、現状の林業に関して気になっていたのが、「スギ・ヒノキなどの伐採がメインで、植林ができていない」という課題でした。植林不足の要因として大きいのは人材不足です。国産の木材価格は、輸入木材に押されて下がっているため、ワーカーの林業離れは進むばかりです。そして数少ない林業従事者は、すぐにお金を生んでくれる伐採に偏りがちです。つまり、植林が行われていないのは、複合的な原因によるものなのです。
伐採した木は木材として収益を生みますが、植林した木が収益を生むまでには数十年の時間がかかります。だからといって伐採が中心の林業を続けていると、将来の原木不足や土砂災害、生態系の破壊といった問題が深刻化していきます。さらに、現在の日本では「植える」というスキルをもつ人材は不足しているので、いざ植林が必要となったときに、できる人がいない、という状況も課題だと思いました。
このサイクルを変えるために、植林ができる人材育成を兼ねて、ドングリがなるブナ科の樹木の植林を行うことを決めました。ブナ科の食物ならドングリが落ちて自生するので、里山の環境保全につながりますし、鹿やイノシシなどのエサにもなるので獣害対策につながります。
 ――伐採をしないとなると、直近の収益はどのように生むのですか?
まず、「植林」という体験を販売することによって収益を生むことができます。小中高大生の教育プログラムや企業のチームビルディング、熊野古道を訪れた観光客の方に植樹してもらうなどの形でビジネスにつなげることができます。
さらに、環境に対して課題意識をもつ企業さまに向けて、「植林によって環境保全を行いませんか?」と提案することも可能です。「SDGsに取り組んでいる」というアピールになるため、前向きにご検討くださる企業さまは増えています。私はこうした取り組みを「広告宣伝業としての林業」と呼んでいます。
――伐採をしないとなると、直近の収益はどのように生むのですか?
まず、「植林」という体験を販売することによって収益を生むことができます。小中高大生の教育プログラムや企業のチームビルディング、熊野古道を訪れた観光客の方に植樹してもらうなどの形でビジネスにつなげることができます。
さらに、環境に対して課題意識をもつ企業さまに向けて、「植林によって環境保全を行いませんか?」と提案することも可能です。「SDGsに取り組んでいる」というアピールになるため、前向きにご検討くださる企業さまは増えています。私はこうした取り組みを「広告宣伝業としての林業」と呼んでいます。
未来に向けて安全な環境づくりを になっていける林業を
――実際に「伐らない林業」を始めるにあたって、どこから着手したのですか?
まず山を購入して植林を行いました。下請け業者として植林を行う方法もありましたが、自社の土地にブナ科の木を植えて里山の環境をつくりたかったので、山を買うところからスタートしました。また、一般的な林業では苗木業者から購入して植林をおこないますが、中川では苗木づくりから手がけることにしました。
――なぜ苗木づくりにも取り組むことにしたのですか?
ひとつには、紀州備長炭(和歌山県の重要な特産品のひとつである白炭)の原木であるウバメガシの苗木をつくりたい思いがありました。ウバメガシは和歌山県にとって重要な樹木であるにも関わらず、現状では高知県などから購入した苗木で植林が行われています。地域内で経済を回すためにも、自社で苗木づくりから取り組もうと決めました。
また苗木の中には、見た目を美しくするために農薬などの薬剤が多く使われているものもあります。森林は未来の水資源と深く関わってくるので、自社で育てた安全性の高い苗木で植林を行い、子どもたちの明るい未来につなげたいと考えたのです。
株式会社中川
2016年創業。「木を伐らない林業」を提唱し、苗木つくりや植林、山林管理などを手がける。林業の関係人口創出や地域活性化などの取り組みが注目され、第10回「GOOD ACTIONアワード」入賞、第14回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞審査委員会特別賞など受賞歴多数。