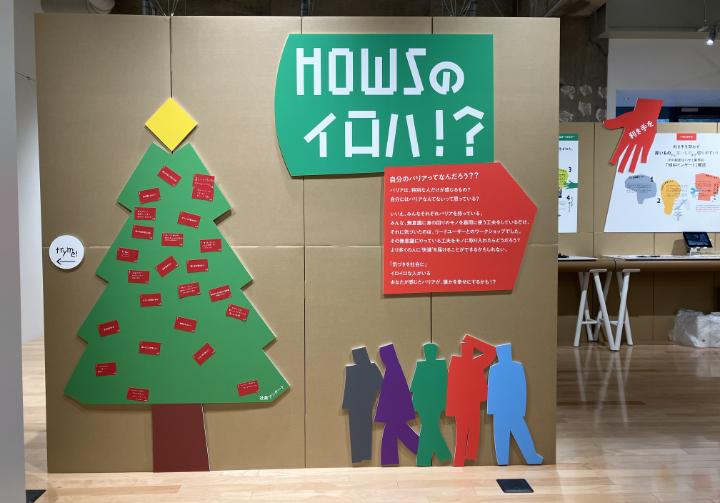組織の力
2017.07.03
「働き方改革」を支援する、人工知能を活用した組織開発〈後編〉
組織の活性化に影響を与える、複雑な行動要因をAIが分析・抽出

働き方改革をすすめる大手企業を中心に導入が増えている『Hitachi AI Technology/組織活性化支援サービス』。後編では、同サービスで活用されている人工知能を使っての具体的な施策や事例について、同サービスの主任技師の小川祐一さんと、サービスデザイン研究部の辻聡美さんにお伺いした。
企業ごとに最適な残業時間を
導き出すことができる
「他には、コールセンターのオペレーター向けに導入したケースがあります。シフト制で、毎日メンバーが異なるので、仮説としては、お客さまに商品を売り込むスキルの高いメンバーが揃っている日が、チームとしての業績も高いだろうと想定していたのですが、実際は違っていていました。オペレーターたちが、より活発にコミュニケーションを図り、いきいきと働いている組織活性度の高い日が業績も伸びていたのです。『同僚たちと連携がとれている日は、一歩踏み込んだ提案ができている』などの仮説を立て、今はその検証と他のチームへの転用に取り組んでいます」(辻さん)
また、残業時間が3時間までなら、組織活性度は変わらないが、3時間を超えると組織活性度が低くなってしまう。そのため『まずは1日3時間の残業を目標に仕事をしよう』という目標を立てた企業もあるという。
「残業を極力減らしたほうがいいというのは、誰もがわかっていること。しかし、組織や会社によって業務の進め方ややり方が違いますので、一律に何時間がいいとはなかなか言えません。しかし、このサービスなら、会社にとっての最適な時間をデータの収集や分析、そして検証によって導き出すことができます」(小川さん)
仮説通りの結果であっても、
分析結果をもとに皆で話し合える機会になる
実際に、これまでの『Hitachi AI Technology/組織活性化支援サービス』を利用したお客さまの評価は、どのようなものだったのだろうか。
「大きく分けると2タイプあります。1つは、思っていた仮説を確認できたという声と、もう1つは、想定していなかった結果になって、新たな気づきが得られたという声です。どちらも評価をいただいており、後者においては、たとえば、世代間によって組織の活性化に影響を与える行動要因が異なっていて、若い世代にはコミュニケーションの頻度を増やすことが必ずしも良いとは限らないという結果が出たことがあります。それが世代間の価値観や考え方の相違なのか、または仕事のやり方の違いなのかは、検証しながら見極めていく必要はありますが、いずれにしてもデスクワークに集中できる時間とのバランスが大切なようです」(小川さん)
「また、お客さまが事前に想定していた結果が出た場合であっても、このサービスによって可視化できたことで、従業員同士が自分達の働き方について議論する場が生まれるという効果があります。たとえば、これまでは『うちのチームって、ここがダメだよな』『もっとこうしたらいいのに』と多くの従業員が思っていても、それぞれの感覚知でしかなく、明確化も共有化もできていませんでした。当社が計測・分析したレポートをお見せすると、想定内の結果であっても『うちのチームって、やっぱりこの人がハブだったんだ。けど、彼だけに頼っていても、ダメだよね』というように、チームの問題についてみんなで話しをする機会になっているようです。そして、そこから合意形成をとって、つぎの改善施策の提案へとつなげています」(辻さん)
しかし、お客さまが新たな施策を行い、効果を実感できるようになるには、時間を要するという課題もある。
「サービスを導入し、そこで見出した組織の課題を解決するための新たな施策の効果を従業員が体感するまでには、どうしても1〜2年のスパンはかかってしまいます。それでも従業員一人ひとりが『Hitachi AI Technology/組織活性化支援サービス』を活用することで幸福感(ハピネス)が高まり、自助努力によって行動改善に取り組めれば、生産性が向上し、より多くの企業でサービスの必要性を痛感してもらえるはずです」(辻さん)
将来は、個別のクライアントだけでなく
業界別や企業規模別の分析にも活用
日立製作所では、蓄積されたビッグデータと人工知能を活用して、将来的には、業界別や企業の規模別に、組織活性度の傾向を分析できるようなサービスなども視野に入れているようだ。
『働き方改革』への企業の関心度の高まりを受け、新たな施策や新たな制度の導入はさらに加速していくだろう。人工知能を活用して、組織を活性化し、組織力を高めていくという『Hitachi AI Technology/組織活性化支援サービス』は、チームワークを得意とする日本の文化にも合っており、今後もますます注目を集めそうだ。