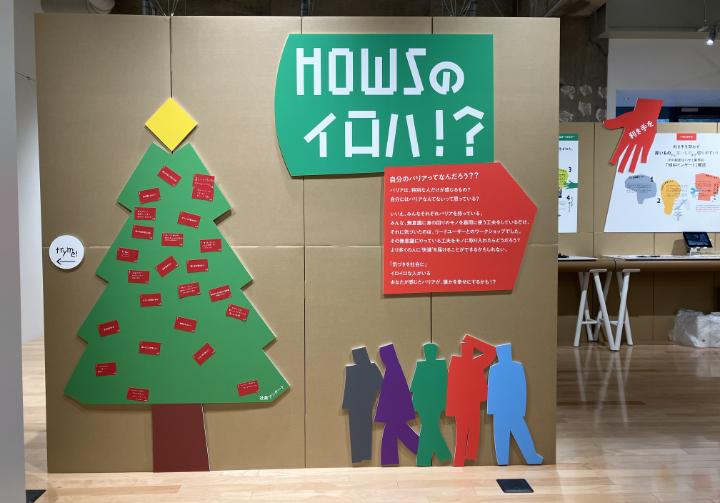ライフのコツ
小中学生が働き方を考える職業体験イベント
生きる力を身につけるミニフューチャーシティの試み

小・中学生が自分たちでつくったモノやサービスを店で販売し、仮想の電子通貨で給料をもらって買い物をするという一連の経済活動を通じ、働くことの意味を考える職業体験イベント「ミニフューチャーシティ」が7月30日、グランフロント大阪で催された。こどもたちが、変化する状況の中で考え、行動し、失敗しながら自分の居場所を見つけていく様は、まさに実際の街で起こる人間ドラマを見ているようだ。ミニフューチャーシティの立ち上げをリードした京都大学総合博物館の塩瀬隆之准教授、こどものまちづくりを担当するNPO法人cobon代表理事の松浦真さん、アプリ・システム開発を担当する株式会社GOCCO.代表取締役の木村亮介さん、プログラム内容の開発、進行を担当するこどもみらい探求社共同代表の小竹めぐみさんに取り組みへの思いを尋ね、ミニシティの中のこどもたちの様子をつぶさにのぞいてみた。
- したたかに生きるための
擬似職業体験を - 仮想の街、ミニフューチャーシティが設営されたグランフロント内のナレッジシアターに一歩足を踏み入れると、「みらい素材屋」「みらい美容室」「みらいカメラマン」「みらいゲームセンター」など16の店がひしめきあっている様子が目に飛び込んでくる。店の売り込みに忙しい子、低迷する売上げに表情が冴えない子、嬉々として買い物に興じる子、商品を黙々とつくり続ける子...。それぞれが自由に働き、消費しながら人、店は刻々と変化をとげ、街そのものが生き物のようだ。

- ミニフューチャーシティの大まかな仕組みはこうだ。こどもたちは、まず割り当てられた店で30分働くと給与が支払われる。その後は同じ店で働き続けてもいいし、新たな店に転職しても、起業してもいい。得た収入で自由にモノやサービスを買うことができ、お店は売り上げを投資に回してさらに売れるように工夫ができる。
一人ひとりに「LITコイン」と呼ばれる三角形の端末が配られ、どこで働き、どれだけ稼いで、何にどれくらい支出したかすべての履歴を記録できる。各店にはレジの役割を果たすタブレットが置かれ、買い物をする際は「LITコイン」を近づけると「ハッピー」という通貨単位でお金のやりとりができるようになっている。 - ミニフューチャーシティの立ち上げメンバらに声掛けをした京都大学総合博物館の塩瀬准教授は2年前にこのプログラムを始めた狙いについて「幼稚園から小、中、高、大学と社会への入口に近づくにつれて、こどもたちが目の輝きを失っていくかのような状況はなんともったいないことかと思っていました。こどもたちは大人たちに与えられた環境しか知らない「井の中の蛙」になりがちで、外の世界が存在することを知らないからです。この状況を脱するには、もっと社会の中で自分がどの位置にいるかを知ったうえで、社会に出るまでに何をすべきかを戦略的に考えるような機会が必要だと思っているんです。そのためには、たとえそれが疑似体験でもいいから、できるだけ早い時期に働いてみるという体験をすることが重要だと考えました」と語る。
-
 右)京都大学総合博物館 塩瀬隆之准教授
右)京都大学総合博物館 塩瀬隆之准教授
そこで目をつけたのが、NPO法人cobonが2007年から続けていた「ミニ大阪」、「ミニシティ」の取り組みだ。「こどもの職業体験プログラムとして商業的に成功しているサービスはうまくつくりこまれていて、大人の真似をすることで、よい練習ができます。しかし、そこでの体験には偏りがあり、大人が決めた役割に就き、決められた作業をこなすだけ。こどもたちがそれぞれの仕事の歯車になって一つのスキルを身につける、という前提に立ったプログラムが多いと思います。
それに比べミニシティは、街の中の仕事や、生活の中で求められるもの、そして、そこで必要とされるサービスに気づき、新たな仕事が生まれていく社会の仕組みが自然に理解できるようになっています。歯車同士がうまくかみ合わなくて、動かない歯車、空回りする歯車がたくさんいて、どんな歯車がそこに必要かに自分で気づくことが大切です。そして、自分たちで考えたモノやサービスが"売れない"、といった失敗も経験できる。これこそ真のキャリア教育なんです」と塩瀬准教授。そして2015年8月、ミニシティに最新のICTをとリ入れた進化系としてミニフューチャーシティがスタートした。
- 状況を読み、
しなやかに新しいもの生み出すこどもたち - ミニフューチャーシティに参加する親子向けには開催1週間前に住民説明会が開かれる。そこでは、イベントの狙いなどの説明を受けたあと、途上国と先進国のチームに分かれ、どうすれば両国が共に発展できるかを考える貿易ゲームを通じて、協力することの大切さを学ぶ。そして本番当日は、店で適材適所の役割を果たせるよう全員で得意なことを自己紹介する機会を設けている。それが終われば、あとはこどもたちの世界に委ねられる。
- こどもたちは同じ店でも状況に合わせてしなやかに業態を転換してみせる。たとえば「みらいコップ屋」はもともと紙コップを売る店だったが、昼過ぎにはピラミッド状に重ねた紙コップにボールを当て、倒した数が多いほど紙コップがもらえるゲーム業に変化していた。聞けば、午前中はまったく紙コップが売れず、ひまを持て余して紙コップを重ねるゲームを楽しんでいるうち、これをサービスにしようと思いついたのだという。ボールは「みらい素材屋」から仕入れた紙粘土でつくった。
-
 「みらい素材屋」では商品が飛ぶように売れる。他の店がみなディスプレー素材を購入するからだ。商売繁盛で店員もみな機嫌が良い。
「みらい素材屋」では商品が飛ぶように売れる。他の店がみなディスプレー素材を購入するからだ。商売繁盛で店員もみな機嫌が良い。
 お客を呼び込むためサービスをふやしていく「みらいゲームセンター」。ゲーム機は「みらい建築屋」に外注している。
お客を呼び込むためサービスをふやしていく「みらいゲームセンター」。ゲーム機は「みらい建築屋」に外注している。
- ミニフューチャーシティを際立たせているのは、街の経済活動が電子通貨でやりとりできたり、一人ひとりの行動履歴をビッグデータ化して分析できるようにするなど、街を裏で支えるICTの存在だ。AI(人工知能)やIoT(モノどうしをつなぐインターネット)といったテクノロジーの進歩により今ある職業の多くは十数年後になくなっているという予測もされる中、塩瀬准教授は、「人は物心がついてから後に、新たに生み出された技術をテクノロジーと呼んで恐れを抱きがちです。それならば未来を先取りした技術にあらかじめ触れ、使いこなせる側に回ればいいんです。AIもIoTも最初から慣れてしまえば、今の大人のように、テクノロジーというだけで闇雲に恐れるという諦めムードを払しょくできるのではないかと考えています。時代、社会制度が変われば、必要な道具と技術も変わるわけで、過去に覚えたスキルや知識は使えなくなるものだということを知ることも、また生きる力になります」とICTを取り入れた狙いを語る。
-
 左)株式会社GOCCO. 木村亮介さん
左)株式会社GOCCO. 木村亮介さん
ミニフューチャーシティのアプリを開発した株式会社GOCCO.の木村さんは、こども向けなのでできるだけ説明を伴わずに直感的に使い方を理解できるデザイン、仕組みにするために工夫を凝らしたという。「はじめは使えるかどうか心配でしたが、こどもたちは5分、10分でものにします。むしろ周囲の大人がついていけないくらい」と笑う。もう一つアプリ開発で重視したのは「余白」だ。そこには「あまりがちがちにつくりこみをせず隙を残しておくことでこどもたちが新しい使い方を考え出してほしい」との思いがある。
- この日も、個人消費を活発にする狙いで、午後から1店当たりの社員数を4人に制限をかけたところ、はじき出されたこどもたちが仕事を求め、ハローワークに列をつくった。しかし仕事に就けない状況が続くと、一部のこどもたちは無償で店の手伝いを始めたのだ。これに対し、店長が店から個人に送金できる機能を使ってアルバイト代を支給したという。「ただ働きさせて申し訳ないと思ったのでしょう。誰もそんな使い方を教えていないのに自分たちで新しい使い方を発見していくところは毎回すごいなと思わされます」と木村さん。
-
 ハローワークにある端末で、振り込まれた給料を確認し、同時に転職希望を出す。
ハローワークにある端末で、振り込まれた給料を確認し、同時に転職希望を出す。
 就職口が減ったことでハローワークに、職を探すこどもたちの列ができる。
就職口が減ったことでハローワークに、職を探すこどもたちの列ができる。
- 大人はコントロールしようとせず
いかに手放すかが大事 -
 こどもみらい探求社 小竹めぐみさん
こどもみらい探求社 小竹めぐみさん
グランフロント大阪でのミニフューチャーシティの開催は今年で3回目を迎える。
プログラムの開発、進行を担当するこどもみらい探求社の小竹さんはこの3年間の変化について、「かかわる大人のスタッフが、待つこと、手放すことができるようになった」と言う。「他人とうまくかかわれない子がいたり、運営側の意図しない変化が起こると、私たちはついつい口を出したり、方向を修正しようとしてしまっていました。でもそれがこどもたちの考える力を止めてしまっていることがわかり、今では極力コントロールしようとせずこどもたちのやりたいように任せています」と話す。 - 「みらい掃除屋」で働いていたある子が、仕事の依頼がまったく入らないので、街の中を無償で清掃して回っていた。「自分のやりたいと思う店に転職してみたら」とアドバイスをしたくなるところだが、大人は声をかけず見守っていた。するとその子に対し給与とは別に「感謝」の気持ちを示す「いいね」シールが集まり出したのだ。その子にとっては、それが掃除を続ける励みとなり、「感謝」が仕事をする動機になっていった。また、掃除を続けるうちにごみの中に「お宝」があることを発見した子もいた。ゴミの中から綿だけを選別すると、綿の手触りのよさをアピールし、「気持ちいいよ」と呼びかけながら店で売り始めたところ、買ってくれる客が現れた。掃除屋の新事業としてリサイクル事業がスタートしたのだ。
また、「みらい建築屋」で働く男の子は、周りのこどもたちとうまく意思疎通が図れず、一人ぼっちでいる時間が多かった。一人こつこつとゲームをつくり、「みらいゲームセンター」に売りこんだところ採用され、キラーコンテンツになった。 - 小竹さんは「ミニフューチャーシティの成果として、『どれだけ起業するこどもたちがいたか』、とよく聞かれます。確かに起業は目立つし華々しいけれど、それだけがすごいことではありません。つくるのが得意な子もいれば、売るのが上手な子もいる。それを縁の下で支える子もいる。そのままの自分でも街でできることがあるんだということに気づき、自信を得ることが何よりの経験になると思っています。ある親御さんからも『待つことがこんなに大事にされているプログラムはないですね』と言われ、自分たちのやっていることが再認識できました」という。
-
 なかなかお客の来ない「みらい美容室」前では、店員が積極的に営業。
なかなかお客の来ない「みらい美容室」前では、店員が積極的に営業。
 午後になると「みらい美容室」も大繁盛。スタッフ全員がフル稼働。
午後になると「みらい美容室」も大繁盛。スタッフ全員がフル稼働。
- 学校で適応できないこどもも
街ではいきいきとする -
 NPO法人cobon 松浦真さん
NPO法人cobon 松浦真さん
ミニフューチャーシティの前身であるミニ大阪を立ち上げ、ミニシティ、ミニフューチャーシティへと発展させながらこどもの職業体験イベントに10年間かかわってきたNPO法人cobonの松浦さんは、こどもを参加させる親の思いについて「当初の頃と比べ、プレイフルラーニングや探求という言葉も浸透し、今ではリピーター率が60%になっています。親御さんには、こどもが持ついろいろな可能性を引き出す体験をさせ、答えのない未来の社会を柔軟に受け入れてポジティブに楽しむ力をつけてほしいという思いがあるようです」と分析する。そして長年こどもの職業体験にかかわってきて感じるのは「街にハレとケがあるとすれば、ハレの瞬間を引き起こすのは、場を引っ掻き回すトリックスターの存在。その多くが、学校では周りと合わなかったり、不登校を経験したりしたこどもです。そのこどもたちは用意されたゲームだとすぐにあきてしまいますが、ミニフューチャーシティではイキイキと輝いています」と、ミニフューチャーシティがこどもたちの本来持っている力を発揮する場になっていることを強調する。
- 毎回大人の想像を超えるこどもたちの発想に驚かされることが多いミニフューチャーシティを今後どのように発展させていこうとしているのだろうか。「ミニフューチャーシティでモノやサービスを売ったり、買ったりしながら経済の仕組みを知ってもらうとともに、そうした活動を通じて自分たちの街がどう変わっていくのか俯瞰して見る視点を持つことで、『将来は大学へ行って大企業に就職する』という、凝り固まった人生観から脱却し、それとは異なる生き方があるということに気づいてもらう場にしたい。そのためにこの街ならではの新しい取り組みをどんどん採り入れていくことができれば」と松浦氏。こどもの限りない可能性を発揮する場を目指し、ミニフューチャーシティはさらなる進化を遂げようとしている。
-
 「みらいシティデザイナー」には各店から様々な相談が持ち込まれる。
「みらいシティデザイナー」には各店から様々な相談が持ち込まれる。
 「みらいカメラマン」の出張サービス。店のPR写真を撮ってまわる。
「みらいカメラマン」の出張サービス。店のPR写真を撮ってまわる。
塩瀬隆之
京都大学総合博物館准教授。2014年まで2年間、経済産業省産業技術環境局課長補佐として技術戦略を担当し、教育研究の現職に復職。小中高校におけるキャリア教育、企業におけるイノベータ―育成、熟練技能伝承に関する研究、講演を精力的に行っている。
街づくり体験型ワークショップ「こどものまち」や海外や異文化での越境学習体験を通じて、こどもや大人のキャリア支援を行っている。ミニフューチャーシティの前身である「ミニ大阪」を2007年に始めた。
「楽しさぞくぞく開発中」をコンセプトに、タッチパネルに置くだけで音楽が鳴り出す特殊な紙の開発や、3Dプリンターを使ったプロダクト開発など、WEB・アプリを中心とした新しいものづくりを提案。こども向けのITイノベーション教室も開いている。
保育士経験のある2人の女性が創業。人材育成、組織・コミュニティ育成事業のほか、イベントの企画運営、コンサルティング事業などを行っている。
文/山口裕史 撮影/MANA-Biz編集部