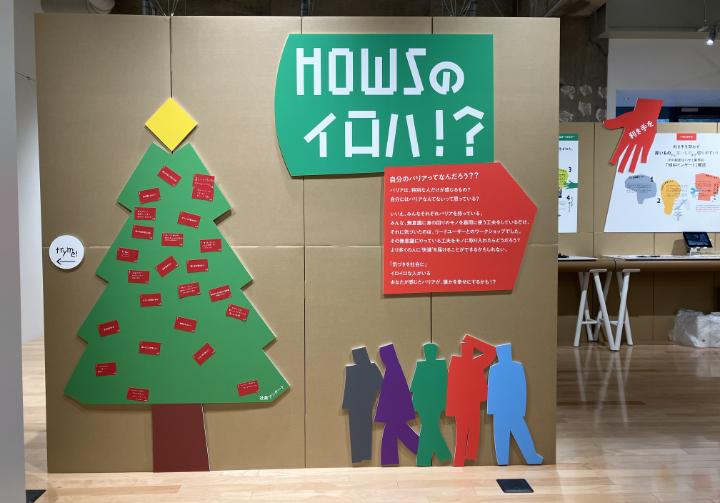ライフのコツ
2018.01.24
21世紀に求められるPISA型学力-後編
これからの日本の教育のゆくえは?

前編では、PISA(生徒の学習到達度調査)の概要と2015年に実施された最新の調査結果を紹介した。続く後編では、PISAの調査結果を受けて、国内ではどのような教育施策が展開されてきたのかを探っていく。身につけた知識を社会生活で直面する課題に活用する力、いわゆる「PISA型学力」の育成が重要視されるようになった背景から、親としてできることまで、引き続き、文部科学省国立教育政策研究所研究員の小田沙織さんに伺った。
- 「PISAショック」をきっかけに
国を挙げた教育改革がスタート - 2000年から3年おきに行われているPISA(ピザ)だが、2003年、2006年の調査において、日本は順位・平均得点とも低下した。
- 「関係者の間ではこれを"PISAショック"と呼んでいます。参加国数の増加も考慮すると、そこまで大きな低下ではないとも考えられるのですが、メディアでは大きく報道されました。そして、この"PISAショック"を受けて、社会的にも政治的にも日本の教育が問題視されるようになったのです。なかでも、2002年に実施された学習指導要領による、いわゆる"ゆとり教育"に対する批判は大きく、"PISAショック"当時の第1次安倍内閣は2006年に教育再生会議を立ち上げ、学習指導要領の改訂や教員免許更新制度の制定などを進めました」
 出典)国立教育政策研究所
出典)国立教育政策研究所- 教育再生の一環として2007年に始まったのが、全国学力・学習状況調査だ。児童・生徒の学力や学習状況を全国的に把握・分析して教育施策の成果と課題を検証し、改善を図ることを目的としている。全国の小学6年生と中学3年生の全員(※)を対象に実施し、知識に関する問題と知識の活用に関する問題の2種類が出題される。
※年度によっては全員調査ではない。 - 【活用型問題の例】地図を見て公園の面積を求める問題
 出典)平成19年度全国学力・学習状況調査(小学6年生算数)
出典)平成19年度全国学力・学習状況調査(小学6年生算数)- 【知識型問題の例】平行四辺形の面積を求める問題
 出典)国立教育政策研究所
出典)国立教育政策研究所- 「前編でも紹介した公園の面積を求める問題は活用型問題の一例ですが、正答率は18.2%でした。一方、単純な平行四辺形の面積を求める知識型問題の正答率は96.0%であり、その差は明らかです(正答率は2007年度の実施当時)。平行四辺形の面積は求められるのに、それが地図上の公園になったとたん、周囲の状況を読み解き、必要となる情報を探し出すことができなくなるんです。この結果からも、日本の児童は、基礎的な知識や技能は身についていても、それを実生活の場面に活用する力に課題があることがわかります」と語る小田さん。
- こうした問題意識から、2008年に改訂された学習指導要領には、「生きる力をはぐくむ」という表現で、知識や技能の習得とともにこれらを活かした思考力・判断力・表現力の育成に力を入れることが明記された。この学習指導要領は、小学校では2011年度、中学校では2012年度、高校では2013年度より全面実施され(いずれも2〜3年の先行実施期間あり)、現在に至る。そして、2017年3月には、2020年度より実施される次期学習指導要領が公示された。
- 「今回の改訂の大きな特徴が、『(児童・生徒が)何ができるようになるか』を明確化している点です。従来の学習指導要領は「(教師が)何を教えるか」が中心でしたが、今回は『何のために学ぶのか』という学習の意義の共有に重きを置いています。これは、PISAの結果で見えてきた、実生活との関連付けや意欲・関心の伸張といった課題への対応策とも重なります」
- アクティブ・ラーニングで
「PISA型学力」を育成する - 次期学習指導要領でも謳われているのが、児童・生徒による主体的・対話的な学び、いわゆる「アクティブ・ラーニング」だ。これは、ただ知識を覚えるのではなく持っている知識を活用するという、まさに「PISA型学力」を育成するための学びだと言える。
- ところで、知識偏重型と言われてきた日本の教育だが、2012年のPISAでは興味深い結果が出ている。数学を勉強する際の方法について尋ねた質問事項では、解法パターンを覚えるなど暗記的な学習をしている生徒の割合は少なかった。ただ丸覚えするのではなく、要点を押さえて応用が効くような学習をしている生徒の割合が比較的高かったのだ。日本の生徒は必ずしも暗記型学習者ではないという結果が出た一方で、今までに学んだ知識との関連付けをしながら学んでいる生徒の割合も少なかった。国際的に見て関連付けができている生徒は難問の正解率も高く、「この部分をどう伸ばしていくかが、今後の課題」と小田さんは言う。
- 「土台となる知識をしっかりと身につけること、そして、その知識を活用する力をつけることが、学びの両輪となります。知識を活用する力を育てるという意味では、2000年度からスタートした『総合的な学習の時間』を通した能動的な学びが有効だったと考えています。昨今は『アクティブ・ラーニング』という言葉で表現されていますが、総合的な学習の時間やアクティブ・ラーニングの目的は、知識の定着と活用、つまり、いわゆる『PISA型学力』をつけることです。小中学校では従来から班活動などを通して実践してきたことですが、高校や大学でもこれを強化していくという流れになってきています。2020年の大学入試改革も含めて、学びのスタイルは大きく変わるでしょう」

- 学力や意欲を支える
「生徒のwell-being」を考える - 2015年のPISAでは、学力面の調査に加え、「生徒のwell-being(生徒の「健やかさ・幸福度」)」の調査も初めて実施された。学校への質問(校長などが回答)と生徒への質問を通して、生徒の生活満足度、テストへの不安、学校への所属感、いじめ、運動と食習慣、学校外でのICT活用などについて調査が行われた。なかでも、生徒に生活満足度を10段階で尋ねた質問では、日本の生徒の平均値は6.8(43位)とOECD平均7.3を下回った。
- この結果について小田さんは「データを見ると、日本をはじめ韓国、台湾、マカオ、香港と東アジアの国では生活満足度が低くなっており、これは文化的要因も大きいのではないかと思われます。43位という順位だけを見ると低いと感じますが、10中の6.8というのは決して悪い数字ではないとも思います。とはいえ、国際的に見て日本の生徒の生活満足度が相対的に低いというのは事実です。そのほか、いじめについてはOECD平均よりは低く、ICTの活用については宿題のため・余暇のため、いずれの目的においても利用時間はOECD平均より短くなっています。いずれもこの調査だけでは判断はできませんが、興味深いデータだと思います」と分析している。
- 一方で、「朝食を食べた生徒は科学的リテラシーが高い」、「親がこどもの学校での活動に関心があると、こどもの意欲や生活満足度は高くなり、生活への不満や学校で寂しいと感じる度合いは低くなる」という結果も出ている。
 出典)Parents’interest in child’s activities at school and their well-being
出典)Parents’interest in child’s activities at school and their well-being- この結果について小田さんは「親のこどもへの関心は、教育においてとても重要な要素だということがわかります。また、別の調査(※)によると、たとえ家庭の社会的・経済的背景が良くなくても、こどもが学習に充てる時間が長ければ、学力が高くなる傾向にあることがわかっています。学力と学習時間の相関関係は、家庭の背景には左右されないということです。つまり、親がこどもに積極的に関わり、学習に向かわせる環境があれば、不利な状況も克服できるということでしょう」と言う。
- ※平成25年度全国学力・学習状況調査(きめ細かい調査)の結果を活用した学力に影響を与える要因分析に関する調査研究(お茶の水女子大学)
- 小田さんが挙げた同調査では、学力が高いこどもの保護者には、次のような傾向があるとしている(一部抜粋・改定)。小田さんは、「上から物を言うようで恐縮ですが」と前置きをしたうえで、「これを、読者の方へのメッセージに替えたいと思います」と述べる。
- 【こどもへの接し方】
生活習慣に関するはたらきかけ
読書に関するはたらきかけ
学習に関するはたらきかけ
文化・芸術・自然体験活動に関するはたらきかけ
こどもとのコミュニケーション - 【学校との関わり】
学校の教育に関する意識
学校の活動への参加など - 後編で探ってきたように、身につけた知識を社会生活において活用する力は、今後の多様化する社会における「学力」のスタンダードになっていくだろう。「PISA型学力」という言葉自体も、数年後にはなくなっているかもしれない。求められる力は、時代によって変わっていく。ただ、親がこどもに関心を持つことの重要性は、いつの時代も変わらない。まさに、教育の本質的要素の一つなのではないだろうか。

小田 沙織
2006年文部科学省入省。初等中等教育局教育課程課、同局参事官付(学校運営支援担当)、教職員課などの勤務経験を経て、2015年4月より現職。国立教育政策研究所では、OECD-PISA調査の国内での実施や調査結果分析のほか、同研究所のプロジェクト研究にも携わる。
文/笹原風花 撮影/石河正武