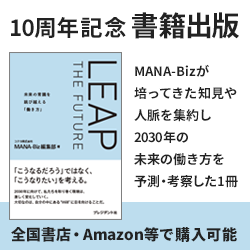組織の力
「都市のイノベーションと場の役割」~エッジシティにおける場の可能性~
Catalyst BA ファイナル・ダイアログ

2011年4月、二子玉川を舞台として産官学の共創による街づくりの実験場としてオープンした『カタリストBA』は12年間の活動を経てその役目を終え、2023年6月末でクローズした。その活動の軌跡を振り返り、これからの街づくりを語ることを目的として開催された『Catalyst BA ファイナル・ダイアログ』。冒頭にカタリストBAの立ち上げに尽力した多摩大学大学院教授の紺野登氏による基調講演。続いて東京大学大学院教授の筧氏、東急株式会社常務執行役員の東浦氏を加えた3人で「都市のイノベーションと場の役割」をテーマにパネルディスカッションが行われた。モデレーターはコクヨ株式会社の齋藤敦子が務めた。
登壇者
■紺野登氏(多摩大学大学院教授 一般社団法人Future Center Alliance Japanファウンダー) ■筧康明氏(東京大学大学院情報学環・学際情報学府 教授) ■東浦亮典氏(東急株式会社 常務執行役員) モデレーター:齋藤敦子氏(コクヨ株式会社BAアーキテクト)
イノベーションを起こすための 都市のあり方と変化
カタリストBAの12年間の活動を締めくくるファイナル・ダイアログは、紺野氏による基調講演でスタート。都市の果たすべき役割や場のイノベーション、カタリストBAでの試みについて語った。

〈紺野氏基調講演〉
加速する都市人口の拡大、すなわち急激な都市化の時代、持続可能性のための都市のイノベーションは私たちの使命です。とくに都市化により自然世界との境界が破れ、複雑化していることは大きな脅威となっています。 また、20世紀は都市と郊外をつなぐ高速鉄道とモータリゼーション、そして垂直移動のためのエレベーターという3つのテクノロジーで分業型労働に基づく現代的都市が形成されました。それが、一世紀経って、シェアードスペースやワーク・フロム・ホームなど、分散・協業型へとシフトし始めました。こうした転換期に、人が創造性を発揮できる都市をめざして『クリエイティブ・シティ・コンソーシアム』が発足、その活動の場としてカタリストBAが開設されました。 私の関わる一般社団法人Future Center Alliance Japan(以下、FCAJ)では、仮説共創のためのフューチャーセンター、プロトタイピングの場としてのイノベーションセンター、社会実験のためのリビングラボという、三様の場からの社会的でオープンな(プレイス・ベースド)イノベーションを提言してきました。
私の関わる一般社団法人Future Center Alliance Japan(以下、FCAJ)では、仮説共創のためのフューチャーセンター、プロトタイピングの場としてのイノベーションセンター、社会実験のためのリビングラボという、三様の場からの社会的でオープンな(プレイス・ベースド)イノベーションを提言してきました。
 場は人々がさまざまな障壁を越え、対話し、行動を起こすために繋がり、そして境界を越えて融合するための結び目(バウンダリーオブジェクト)として重要であることがさまざまな研究からも示されていました。そういう背景のなかで、カタリストBAは多様な境界と人々をつなぐ場の役割を担って生まれてきました。
同時に、二子玉川の立地として、「エッジシティ」というコンセプトに着眼し、郊外でもなく都心でもない、それらの境界における場のあり方を模索してきました。最近はコロナ禍を経て、エッジシティのあり方も進化し、重要度の低い対面の機会コストが激減できる一方、重要度の高い対面の場の価値を最大化する融合のモデルが求められています。その実験としてもエッジシティの場としてのカタリストBAは有効でした
場は人々がさまざまな障壁を越え、対話し、行動を起こすために繋がり、そして境界を越えて融合するための結び目(バウンダリーオブジェクト)として重要であることがさまざまな研究からも示されていました。そういう背景のなかで、カタリストBAは多様な境界と人々をつなぐ場の役割を担って生まれてきました。
同時に、二子玉川の立地として、「エッジシティ」というコンセプトに着眼し、郊外でもなく都心でもない、それらの境界における場のあり方を模索してきました。最近はコロナ禍を経て、エッジシティのあり方も進化し、重要度の低い対面の機会コストが激減できる一方、重要度の高い対面の場の価値を最大化する融合のモデルが求められています。その実験としてもエッジシティの場としてのカタリストBAは有効でした
 最後に「都市はだれのものか?」という問いについて考えたいと思います。
今世紀に入って、オキュパイ・ウォール・ストリートのような街頭デモが世界中で盛んになっています。市民主体で未来をデザインしようという動きがあり、市民のための都市空間、ユーザー主体での街づくり活動がさまざまな場所で始まっています。
最後に「都市はだれのものか?」という問いについて考えたいと思います。
今世紀に入って、オキュパイ・ウォール・ストリートのような街頭デモが世界中で盛んになっています。市民主体で未来をデザインしようという動きがあり、市民のための都市空間、ユーザー主体での街づくり活動がさまざまな場所で始まっています。
 大きな社会的変化に対しては必ず反作用が起こりますが、市民が都市をつくるという動きも同じです。しかし、作用と反作用を昇華することで次の世界ができるという意味で、触媒として物語を紡ぐ(ナラティブ:既存のストーリーの応用でなく自ら物語っていくこと)ことが大切で、カタリストBA(触媒・語りスト)の本当の価値はこういうところにあったのではないかと思います。
大きな社会的変化に対しては必ず反作用が起こりますが、市民が都市をつくるという動きも同じです。しかし、作用と反作用を昇華することで次の世界ができるという意味で、触媒として物語を紡ぐ(ナラティブ:既存のストーリーの応用でなく自ら物語っていくこと)ことが大切で、カタリストBA(触媒・語りスト)の本当の価値はこういうところにあったのではないかと思います。

出会いの場であり、リビングラボであり 街づくりの基盤としてカタリストBAが誕生
都市作りの潮流とカタリストBAが果たしてきた機能についての基調講演に続いて、紺野氏、東京大学大学院教授の筧氏、東急株式会社常務執行役員の東浦氏の3人でパネルディスカッションが行われた。モデレーターはコクヨ株式会社の齋藤敦子が務めた。まずは自身の取り組んでいる活動にからめて、カタリストBAでの思い出を語った。

〈パネルディスカッション〉
筧:2013年に声を掛けてもらったのがきっかけで、カタリストBAで何が出来るか探索したのが始まりです。リビングラボ、リビングショーケースとして、生きた場所で見せながら新しい成果物をつくっていくという体験をたくさんさせてもらいました。 東浦:東急の二子玉川第1期開発に際して、二子玉川に魅力を感じてもらうにはクリエイティブな街である必要があるという思想の元に発足したクリエイティブ・シティ・コンソーシアムの活動拠点として、カタリストBAの開設に携わりました。
コンソーシアムの活動の場に加えてコワーキングスペース、イベントスペースという3つの役割で運営することになり、さまざまな人の意見を聞きながらトライアルで始めたのが12年前。震災の年だったこともあり、開設当初はソーシャル系のイベントをたくさん開催しました。こうしたスペースは当時全国でも先進的で、創発スペースを運営している人で開設初期にここを見ていない人はいないんじゃないかというくらい見学者が訪れていました。
東浦:東急の二子玉川第1期開発に際して、二子玉川に魅力を感じてもらうにはクリエイティブな街である必要があるという思想の元に発足したクリエイティブ・シティ・コンソーシアムの活動拠点として、カタリストBAの開設に携わりました。
コンソーシアムの活動の場に加えてコワーキングスペース、イベントスペースという3つの役割で運営することになり、さまざまな人の意見を聞きながらトライアルで始めたのが12年前。震災の年だったこともあり、開設当初はソーシャル系のイベントをたくさん開催しました。こうしたスペースは当時全国でも先進的で、創発スペースを運営している人で開設初期にここを見ていない人はいないんじゃないかというくらい見学者が訪れていました。
 齋藤:産官学民のオープンイノベーションとはよく謳われますが、それが人レベルでつながっていたのがカタリストBAだったと思います。筧さんが街全体で実証実験をされていたのは、まさに生きたリビングラボでしたね。
齋藤:産官学民のオープンイノベーションとはよく謳われますが、それが人レベルでつながっていたのがカタリストBAだったと思います。筧さんが街全体で実証実験をされていたのは、まさに生きたリビングラボでしたね。
 筧:リビングラボであるにはトライアルする「余白」がある街だということが重要で、二子玉川が完成されていない街だったことがクリエイティビティを引き出す環境として有効だったのだと思います。
筧:リビングラボであるにはトライアルする「余白」がある街だということが重要で、二子玉川が完成されていない街だったことがクリエイティビティを引き出す環境として有効だったのだと思います。
人と人が出会う場の価値を最大化することが 経済的観点からも重要
続いて二子玉川がエッジシティではなくなりつつあるなかで、エッジ(周縁/先端)であり続けるためにどうあるべきかについて語り合った。
紺野:人と人が出会う場の価値をどう最大化できるかが一番大事で、それは経済的にも重要な観点です。例えばシリコンバレーのようにハイテクが集積すると周辺地価が高くなり、才能ある若い世代が住めなくなる。だから都市機能を融合させて、人と人の出会いの場とハイテクの場などをどう結びつけるかが今後のテーマとなります。
 齋藤:エッジであるためには場が必要だと考えます。人と人がフラットになれる場があるからこそ、異なる意見を持つ人同士が対話し、協業が生まれたりしますから。
東浦:カタリストBAの空間デザインも、人と自然に出会う成功要因の一つだったと思います。円形なので上座、下座がなく、どこかがゆるやかに開いていて密室にはならない設計は効果的だったのではないでしょうか。
齋藤:目的がないまま、創発のための場だけつくって運用に挫折してしまう企業や自治体は多いです。フューチャーセンターやイノベーションセンター、リビングラボを単体で持っていてもあまり意味がなく、融合してカタリスト(触媒)していくことが今の時代のイノベーションにおいて非常に重要です。
紺野:カタリストBAは従来のルールを越えて、プライベートスペース(オフィス)にパブリックスペース(開かれた対話の場)を持ち込んだところが斬新だったのでしょう。
齋藤:エッジであるためには場が必要だと考えます。人と人がフラットになれる場があるからこそ、異なる意見を持つ人同士が対話し、協業が生まれたりしますから。
東浦:カタリストBAの空間デザインも、人と自然に出会う成功要因の一つだったと思います。円形なので上座、下座がなく、どこかがゆるやかに開いていて密室にはならない設計は効果的だったのではないでしょうか。
齋藤:目的がないまま、創発のための場だけつくって運用に挫折してしまう企業や自治体は多いです。フューチャーセンターやイノベーションセンター、リビングラボを単体で持っていてもあまり意味がなく、融合してカタリスト(触媒)していくことが今の時代のイノベーションにおいて非常に重要です。
紺野:カタリストBAは従来のルールを越えて、プライベートスペース(オフィス)にパブリックスペース(開かれた対話の場)を持ち込んだところが斬新だったのでしょう。
カタリストBAの実績を活かし アジャイルな街づくりを
最後に今後の街づくりと場の展開について話し、パネルディスカッションを締めくくった。
筧:カタリストBAは、多くの人にとって出会いの場でもあったからこそ、今後、第二のカタリストBAは必要。その時にどのような設計が可能なのか、ただ円形の場をつくったらいいというわけではないはずで、伝承可能なものと固有なものを整理して読み解く必要はあるでしょう。
私個人としては、リビングラボやリビングショーケースとして、見せながらつくるという意味でカタリストBAが機能していました。つくりながら見せる場であるためには、日常の文脈をある程度断ち切って異世界である必要があると考えます。カタリストBAはオフィスフロアにあってエレベーターを一度乗り換える必要があるので、日常の地続きではなく異世界をつくりやすい環境だったのではないでしょうか。
紺野:「アジャイルシティ」、つまりアジャイル開発で街をつくりながら、ダメなところはスクラップアンドビルドの発想を持つということを提案したいです。
例えば「イノベーション・ディストリクト」という、大学や商業、住宅などイノベーションに必要なものを特定地区(ディストリクト)に集積させ、その地域の経済エンジンとするという考え方が世界中で注目されています。
単に住みやすい街というだけではだめで、雇用を生み出すなど具体的にどういう経済効果があるのかを考えて街づくりに投資をする。外国の人と一緒に住むためのゾーニングはどう考えるのか、などの視点も重要になってきます。これを主導し実践するには、行政だけでも企業だけでも難しいでしょう。
東浦:二子玉川の豊かなライフスタイルが好きな人が集まり同質化してしまっていて、異質なものを投げ込む人が少なくなっているように感じます。買い物に便利な住みたい街としては評価されても、エッジとしての感度を失ってしまうことを危惧しています。
これからは、この街に住む人も含めてエッジを立てていく取り組みは継続していただきたいですね。都市開発の際に、行政からも創発スペースをつくってほしいというオーダーは増えています。東急としても中長期の展望として職住遊がバランスよく混ざった街づくりを考えていますが、二子玉川で成功した要素は他にも展開していきたいと考えています。12年間ありがとうございました。
 齋藤:カタリストBAでの知見も活かして、これからの新しい街づくりに期待したいですね。本日はありがとうございました。
齋藤:カタリストBAでの知見も活かして、これからの新しい街づくりに期待したいですね。本日はありがとうございました。