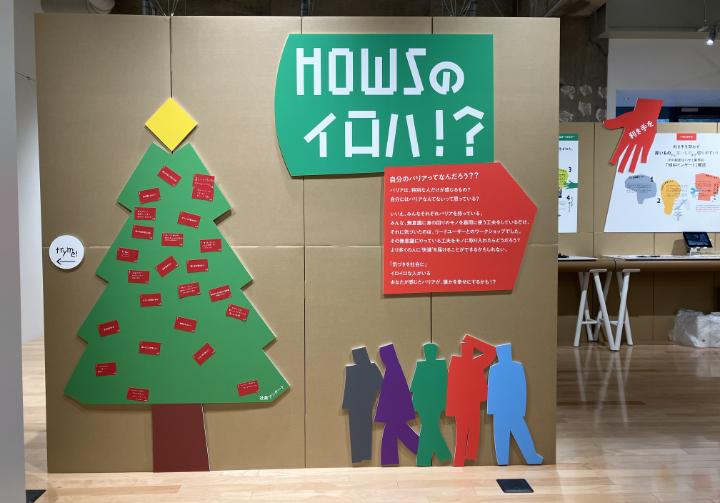組織の力
「エッジシティからの共創の未来」
Catalyst BA ファイナル・ダイアログ

2011年4月、二子玉川を舞台として産官学の共創による街作りの実験場としてオープンした『カタリストBA』は12年間の活動を経てその役目を終え、2023年6月末でクローズした。その活動の軌跡を振り返り、これからの街づくりを語ることを目的として開催された『Catalyst BA ファイナル・ダイアログ』。「エッジシティからの共創の未来」をテーマに、カタリストBAに縁がありエッジの立った活動をする4名による、未来に向けた「場」のあり方についてパネルディスカッションが行われた。
登壇者
■馬場正尊氏(株式会社オープン・エー代表取締役) ■伊藤香織氏(東京理科大創域理工学部建築学科教授) ■神武直彦氏(慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 教授) モデレーター:東浦亮典氏(東急株式会社 常務執行役員)
エッジシティとしての二子玉川で 創出されてきた価値
 伊藤:私は、馬場さんと一緒に『EDGE TOKYO DEEPEN』というイベントの企画監修で3回ほど参加させていただきました。東京の境界(エッジ)である二子玉川で「先端」と「周縁」の2つのエッジを意識しつつ、ビジネスやデザイン、政策制度といったテーマで、それぞれの専門家を招いてトークセッションなどを行いました。とにかくワクワクした思い出があります。
伊藤:私は、馬場さんと一緒に『EDGE TOKYO DEEPEN』というイベントの企画監修で3回ほど参加させていただきました。東京の境界(エッジ)である二子玉川で「先端」と「周縁」の2つのエッジを意識しつつ、ビジネスやデザイン、政策制度といったテーマで、それぞれの専門家を招いてトークセッションなどを行いました。とにかくワクワクした思い出があります。
 東浦:伊藤さんのご専門の一つは「シビックプライド」だと思いますが、どういうものなのかご説明いただけますか?
伊藤:シビックプライドとは、都市に対する市民の誇りのこと。単なる街自慢や愛郷心ではなく、当事者意識に基づく自負心を持って自分たちの住む街をより良い場所にしようとするアクションが、シビックプライドを醸成させます。
アクションの主体はできるだけ多様で小さい単位がたくさんある方がよく、その街づくりのアクションをパブリックスペースで実施することで、より共鳴しやすくなります。まさにカタリストBAは二子玉川のシビックプライドを醸成する役割を担いうると考えていました。
今後については、コロナ禍以降「暮らす」「働く」「遊ぶ」が近接し融合していることが重視されるようになり、15分都市構想などが提唱され始めています。パリの例が有名ですが、そうした都市が増えてきています。
働く場所と住む場所、遊ぶ場所を機能で切り分けて、その間を交通で結ぶ近代の機能主義はすでに限界がきています。私は機能の複合が進んでいく先に融解が起こるのではないかと見ています。二子玉川は早い段階からその可能性を示していて、こうした在り方がエッジシティだからこそ可能なのではないかと考えています。
東浦:シビックプライドは一般名詞化されつつありますが、現状の二子玉川の"シビックプライド度"についてはどう感じますか?
東浦:伊藤さんのご専門の一つは「シビックプライド」だと思いますが、どういうものなのかご説明いただけますか?
伊藤:シビックプライドとは、都市に対する市民の誇りのこと。単なる街自慢や愛郷心ではなく、当事者意識に基づく自負心を持って自分たちの住む街をより良い場所にしようとするアクションが、シビックプライドを醸成させます。
アクションの主体はできるだけ多様で小さい単位がたくさんある方がよく、その街づくりのアクションをパブリックスペースで実施することで、より共鳴しやすくなります。まさにカタリストBAは二子玉川のシビックプライドを醸成する役割を担いうると考えていました。
今後については、コロナ禍以降「暮らす」「働く」「遊ぶ」が近接し融合していることが重視されるようになり、15分都市構想などが提唱され始めています。パリの例が有名ですが、そうした都市が増えてきています。
働く場所と住む場所、遊ぶ場所を機能で切り分けて、その間を交通で結ぶ近代の機能主義はすでに限界がきています。私は機能の複合が進んでいく先に融解が起こるのではないかと見ています。二子玉川は早い段階からその可能性を示していて、こうした在り方がエッジシティだからこそ可能なのではないかと考えています。
東浦:シビックプライドは一般名詞化されつつありますが、現状の二子玉川の"シビックプライド度"についてはどう感じますか?
 伊藤:ひとつ間違えると表層的なブランドのような、別のプライドになってしまうので注意が必要です。この街は自分達が切り拓いてきたという誇りがあるはずですから、それを見失わないようにしたいですね。
東浦:外から見たブランドに自らを落とし込まないようにすることは大切ですよね。
12年前には二子玉川で働くという選択肢はまったくなくて、不動産担当者もここに企業なんて呼べないと言っていましたが、現在は楽天を始めさまざまな企業がオフィスを構えています。ただ、現状は働く人と暮らす人と遊ぶ人が同じ空間に居るだけで、混ざり合ってはないのが課題だと感じています。
神武さんはカタリストBAでワークショップや実証実験などをたくさん実施されていましたが、この場所にどんな価値を感じていましたか?
神武:私はJAXAで宇宙開発に携わっていた経験から、屋外で位置を把握することのできるGPSなどの測位衛星や屋内でそれができるセンサーなどを用いて、人や物の動きを把握したり、さらには物事を俯瞰的かつ緻密に捉える考え方を街づくりや学校教育などに活かす研究教育を行っています。こうしたテーマについて、理論的なことは大学院で行い、実践的なことをカタリストBAで行わせてもらっていました。
私自身、カタリストBAでさまざまなワークショップに参加したり、ここで知り合った方々にラボの空間デザインをお願いしたりしましたし、うちの大学院に入学される方が何人か出てきたりと、非常に多くの出会いがあり、それがいろいろな取り組みの化学反応を起こすことに繋がったと感じています。
「働く人」が、二子玉川といった「住む人」の側に来たことで相互理解が深まり、「地域が育つと人が育ち、人が育つと地域が育つ」という両輪の価値をカタリストBAが提供してきたのではないかと思いますね。
伊藤:ひとつ間違えると表層的なブランドのような、別のプライドになってしまうので注意が必要です。この街は自分達が切り拓いてきたという誇りがあるはずですから、それを見失わないようにしたいですね。
東浦:外から見たブランドに自らを落とし込まないようにすることは大切ですよね。
12年前には二子玉川で働くという選択肢はまったくなくて、不動産担当者もここに企業なんて呼べないと言っていましたが、現在は楽天を始めさまざまな企業がオフィスを構えています。ただ、現状は働く人と暮らす人と遊ぶ人が同じ空間に居るだけで、混ざり合ってはないのが課題だと感じています。
神武さんはカタリストBAでワークショップや実証実験などをたくさん実施されていましたが、この場所にどんな価値を感じていましたか?
神武:私はJAXAで宇宙開発に携わっていた経験から、屋外で位置を把握することのできるGPSなどの測位衛星や屋内でそれができるセンサーなどを用いて、人や物の動きを把握したり、さらには物事を俯瞰的かつ緻密に捉える考え方を街づくりや学校教育などに活かす研究教育を行っています。こうしたテーマについて、理論的なことは大学院で行い、実践的なことをカタリストBAで行わせてもらっていました。
私自身、カタリストBAでさまざまなワークショップに参加したり、ここで知り合った方々にラボの空間デザインをお願いしたりしましたし、うちの大学院に入学される方が何人か出てきたりと、非常に多くの出会いがあり、それがいろいろな取り組みの化学反応を起こすことに繋がったと感じています。
「働く人」が、二子玉川といった「住む人」の側に来たことで相互理解が深まり、「地域が育つと人が育ち、人が育つと地域が育つ」という両輪の価値をカタリストBAが提供してきたのではないかと思いますね。

都心周縁部として多様性を 受け入れる際に重要となる前提とは
神武:また、エッジシティのもう一つの大切な役割に、多様性を受け入れることがあると思っています。今後、海外から人を受け入れていかなければ日本は立ちゆかなくなります。都会の郊外の境目にあるエッジシティにはさまざまな価値観が融合しやすく、多様な人を受け入れる場所になれるはずです。
そうした場は心理的に安全で、懐深く受け入れる場所である必要があります。その前提として大切なのが、コミュニケーションだと思います。
「群盲象を評す」という古くから伝わる絵があります。全体のなかの一部分を見ると、その部分について理解することができるが、そこから全体を理解することはできない。また、同じものを見ていても、別の一部分を見ると、別のことを理解する。つまり、誰もが自分の経験や考えに基づくものの見方をしているのだから、バイアスがあることが当然だ、ということを示した絵です。
多様性を受け入れるためは、人それぞれバイアスがあるという理解の上でコミュニケーションを取れることが更に大切になってきます。さまざまなバイアスにこだわらず、懐深く議論できる場がカタリストBAだったと思います。
馬場:こうして聞いていると、カタリストBAはある人にとっては試行錯誤の場であり、この場で起きている現象自体が研究対象でもあり、思い出の場・自慢の場であり、世界の入り口となる場なのかもしれませんね。私は新しいタイプのパブリックスペースなのではないかと捉えています。
カタリストBAのことを知ったのは、『パブリックデザイン』という雑誌のインタビューで春蒔プロジェクトの田中さんにインタビューをしたことがきっかけでした。こんな場所があれば創発が生まれ、出会いの場になると刺激を受けて、自分でもコワーキングスペースをつくってしまいました。コンセプトはこれまでの計画的都市に対して、「工作的都市」(工作のようにあらゆる人が関わりやすい都市)です。
今取り組んでいることが、実は二子玉川で試行錯誤した経験から繋がっていたのだと感じることがいくつかあって、その一つが「パブリックウエア」という考え方です。次の都市の風景として「パブリックスペースをいかに楽しい場所にして使い倒すか」というコンセプトなのですが、この考えは昔カタリストBAでパブリックスペースをハックするというワークショップをやったことに影響を受けていたと気づきました。
他にも、私が参加している南池袋公園での社会実験があるのですが、その活動の中で「テンポラリーアーキテクチャ」(仮説建築)みたいに街をどんどんつくっていく考え方を思いついたり、今後取り組みたいテーマとして考えている「パークナイズ」(公園化する都市)という、都市を公園と捉えて公園の中で暮らし、働き、学ぶという発想も、二子玉川での取り組みにおおいに刺激を受けたような気がします。

「場」の価値は格上げされ 意図的に選択されるようになっていく
東浦氏:とはいえ二子玉川は「イノベーションは辺境から起きる」という意味でのエッジ(周縁)でもなくなってきているし、エッジが立っているという意味でのエッジは失われつつあると感じています。
再開発としては成功モデルなのかもしれませんが、同質化してエッジ(先端)や多様性が失われつつあるとしたら、これからの二子玉川で新しいものを創発していくのは難しくなるのかもしれません。今後も「場」は必要か、地域と社会との関係性はどうあるべきなのか、皆さんの考えを聞かせてください。
伊藤:先日メタバース内で建築をしている人の話を聴いたのですが、メタバースはパビリオンやインテリアのように目的性が強い空間が向いているのだと感じました。今後メタバースのようなデジタルな空間がますます進んでいくなかで、リアルな空間として「場」の価値が改めて重要になるのではないでしょうか。
これからのリアルな場は、施設に対してひとつの機能が定まっているというよりは、使う人自身が居心地の良さを見いだして、その中で過ごし方や機能を探っていけることが大切なんだと思っています。思ってもいなかった人と出会ってしまうとか、そこに居ればただ気持ちいいみたいな感覚が大事になっていくような気がしています。
神武:場の価値は上がりましたよね。コロナ禍を経て、家で多くの仕事ができるようになったのを楽だと感じる一方で、オンラインでセレンディピティは起こりにくい。会議そのものよりも、その前後の立ち話や飲み会で話すことでセレンディピティが起こったりする...、そのことがとても大切だということを再認識しました。そのための場をよりエッジを立ててつくっていく必要があると思います。
東浦氏:コロナを経てビジネスの場での雑談が減ってしまって、イノベーションが起きなくなってきたので、アプリ上で知らない者同士をマッチングして雑談させるというサービスが出てきているという話を聞きました。
 馬場:仕事でも「これはオンラインでいいです」「これは重要なのでリアルでお願いします」みたいに、リアルな場所でのコミュニケーションの重要性やレベルは圧倒的に上がっています。
気合いが入ると来るみたいに濃淡がハッキリ出るので、運営する側としては場を行きたい空間にしなければならないし、会いたい人でいなければならない。会議そのものは寝ていてもいいような内容だとしても、そのなかで偶然のアイコンタクトとか、会議の後のタバコ部屋での雑談なんかでスパークが起きるみたいなことは、神武さんもおっしゃる通り、リアルな場でしか起こらないですよね。だからリアルな場の価値を再認識したうえで、スパークを起こしたいような場面ではリアルが選択されるようになっていくのではないかと感じています。
東浦:実はこのイベントの打ち合わせも、オンラインでの打ち合わせでは全く議論が進まなかったのに、最後の回だけリアルで集まってみたらどんどんアイデアが出て、リアルで集まって話す価値を感じました。まだまだ話したりないところではありますが、懐かしいエピソードもたくさん聞かせていただきました。本日はありがとうございました。
馬場:仕事でも「これはオンラインでいいです」「これは重要なのでリアルでお願いします」みたいに、リアルな場所でのコミュニケーションの重要性やレベルは圧倒的に上がっています。
気合いが入ると来るみたいに濃淡がハッキリ出るので、運営する側としては場を行きたい空間にしなければならないし、会いたい人でいなければならない。会議そのものは寝ていてもいいような内容だとしても、そのなかで偶然のアイコンタクトとか、会議の後のタバコ部屋での雑談なんかでスパークが起きるみたいなことは、神武さんもおっしゃる通り、リアルな場でしか起こらないですよね。だからリアルな場の価値を再認識したうえで、スパークを起こしたいような場面ではリアルが選択されるようになっていくのではないかと感じています。
東浦:実はこのイベントの打ち合わせも、オンラインでの打ち合わせでは全く議論が進まなかったのに、最後の回だけリアルで集まってみたらどんどんアイデアが出て、リアルで集まって話す価値を感じました。まだまだ話したりないところではありますが、懐かしいエピソードもたくさん聞かせていただきました。本日はありがとうございました。