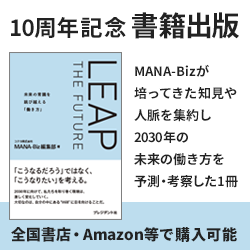トレンドワード
ジェンダーレスとは?企業が取り組む際に配慮すべきポイント、ジェンダーフリーとの違い
知っておきたいトレンドワード33:ジェンダーレス

性差による区別は、無意識にもあらゆるところで行われてきた。ジェンダーに対する意識の高まりもあって、その区別を失くしていこうというジェンダーレスの考え方が教育現場や職場にも広がりつつある。一方で日本はジェンダー・ギャップ指数の低さも際立っている。企業はジェンダーレスをどう受け止め、対応すべきなのか。
ジェンダーレスとは
ジェンダーレスとは「gender(性差や男女の社会的・文化的な差)」と「less(~がない)」を組み合わせた言葉です。社会的・文化的な男女の差がないことをめざして、「男らしさ」や「女らしさ」と呼ばれる役割や職業、価値観、行動などの壁をなくしていこうという考え方です。セックスが身体的・生物学的な性差を表すのに対して、ジェンダーは社会的・文化的に構築された性別を表しています。
ジェンダーフリーとの違い
ジェンダーレスは、男性らしさや女性らしさといった社会的・文化的性差の区別をなくそうという考え方のことです。ジェンダーレスファッション、ジェンダーレストイレなどもそれらの試みのひとつです。 またジェンダーレスは、性別による役務の強制を排除することを意味します。具体的な取り組みとしては、看護婦から看護師、保母から保育士など職業名を変更することや、女性社員だけにお茶くみなどの雑用を強制的しないようにするなど、性差をなくすことなどが挙げられます。 一方、「ジェンダーフリー」(和製英語)とは、社会的に決められている「男性像」や「女性像」にとらわれず、個人の意思で自由に行動や発言や選択をしていくという考え方のこと。 ジェンダーレスが、社会的・文化的な男女の「区別」をなくしていくことをめざすのに対し、ジェンダーフリーは社会的・文化的な男女差が生み出す「差別・格差」をなくしていくことをめざすという違いがあります。
ジェンダーレスが注目されるようになった 背景と歴史
1985年の女子差別撤廃条約や1986年の男女雇用機会均等法の成立から少しずつ男女差が注目されるようになりました。さらにSDGsの目標5に「ジェンダー平等を実現しよう」が盛り込まれてからは、より注目が高まりました。目標5では、性的搾取や早期結婚の慣習、妊娠を望まない女性への配慮などに加えて、女性の発言力や機会が不十分であることが課題視され、政治・経済・公共分野におけるあらゆる決定に女性の意見を十分に反映することが重要な指標とされています。
日本のジェンダー平等の状況
世界経済フォーラムから毎年発表されているジェンダー・ギャップ指数は、「経済」「教育」「健康(医療へのアクセス)」「政治(政治参加)」の4分野におけるジェンダー平等の現状や推移を可視化するため、ジェンダー間のギャップの割合を指数化したもの。2023年のジェンダー・ギャップ指数ランキングにおける日本のランキングは、過去最低の146か国中125位。特に経済分野と政治分野のスコアが低いことがわかりました。 管理職の女性比率が部長相当職で12%と低いことや、国会議員の女性比率が約10%、閣僚の女性比率が8.3%と低い水準であること、女性が内閣総理大臣に就任したことが一度もないことなどが主な要因となっています。 ジェンダー・ギャップ指数の低い国だと認識されると、女性にとって不都合なことが多く、女性が活躍できない国だとみなされ、優秀な人材に働く場として選ばれないことも考えられます。 ジェンダー平等をめざすためには、まず性差の区別による不平等が発生していないかを見直したうえで、評価や手当などの格差をなくしていくという、ジェンダーレスとジェンダーフリー両面での取り組みが求められます。
企業がジェンダーレスを取り入れる際に 配慮すべきポイント
ここからは企業が個人の性別に基づく表現の自由を受け入れ、従業員一人ひとりが自分らしく働きやすい環境をつくるうえで必要な取り組みについて解説していきます。
意識改革に取り組む
企業内でジェンダーレスを取り入れるにあたってまず取り組むべきなのは、意識を変えること。「男らしさ」「女らしさ」とはこうあるべきという固定概念に基づいたルールや慣習が残っていないか見直し、価値観のアップデートを行っていきます。 これまで受けてきた教育や環境の影響も大きいため、反対意見があることも理解したうえで、軋轢をうまないように推進していく必要があります。何が差別にあたるのかを理解したうえで、たとえばジェンダーレスなファッションやメイクなどを受け入れられる環境をつくるため、教育研修や啓蒙活動に取り組むことが大切です。
制服の撤廃や選択肢を増やす
性別による区別をなくすため、女性のみに義務づけていた制服を撤廃したり、制服の選択肢を増やすことも、ジェンダーレスの取り組みとして効果的です。
ジェンダーレス対応の設備を設置する
要望があれば更衣室やトイレなどジェンダーレスに対応した施設の設置を検討する必要もあるでしょう。一方でその結果女性が安心して使いにくくなるなどの行き過ぎた対応がないように注意が必要です。
男性も育児休暇を取得できるようにする
育児休暇や育児時短制度を男性も取得しやすくするなど、「育児は女性がするもの」という固定観念を手放し、職場の雰囲気を変えていくことも重要です。一方で「産休や生理休暇を女性しか取れないのは差別だ」など行き過ぎた議論には注意が必要です。
昇給・昇格の機会に男女差がないか見直す
男女間で賃金格差が生じていないか、生じている場合は何が要因かを確認します。たとえば男性のみに住宅手当や家族手当、単身赴任手当などの手当てが支給されている、昇格試験を男性しか受けられないなど、女性に不利な評価基準や昇進・昇給の機会差になっていないか、確認して是正すべき点があれば見直すことが必要です。
ジェンダーレスを企業文化に根付かせることで、発想が柔軟になったり、モチベーションやエンゲージメントを向上させるなどの影響も期待されます。また、人権を尊重する魅力的な職場として企業イメージを高めていくため、経営戦略としても意義がある取り組みだといえます。性別によるバイアスや固定概念がないかという視点で見直すことから始めてみましょう。